「かしこまりました。それでは、将軍様。この虎を締め上げるための丈夫な縄をご用意ください」
一休はこの返答に、しっくりきていなかった。
「ほほう。縄とな。承知した。どれ、丈夫な縄を今すぐに用意せよ」
家来たちがバタバタと部屋から飛び出し、しばらくすると、注文した通りの太縄をどこからか運んできた。一休はそれを受け取ると、両肩からぶら下げ、右手で縄を振り回しながら叫んだ。
「それでは将軍様、この虎めを屏風から追い出してください!」
「虎を?ここから追い出せと申すか?」
「そうです。だって困ってるんですよね。毎晩抜け出して。だからお願いします。縄で縛り上げますから、さっさと虎を出してください。お願いします」
「虎を……。虎を?」
将軍は狼狽しながら家来たちに目をやった。
「これ、お前たち。ぼさっと見てないで虎を屏風から叩き出せ」
家来たちは思った。「は?」と。
広間にいるいい大人たちの全員が「は?」と思っていた。
いきなり無理難題を横流しされた家来たちは、槍や剣を持ってきて屏風を囲み、突いたり声をかけたり、それなりに「がんばっていまっせ」という素振りを示した。が、無論何の意味も成さなかった。この場がどうして設けられたんだっけ?とか、帰りに虫除け用の線香を買わなきゃいけないんだった。切らしてたから。とか各々が考えていて、誰も真剣に場に臨んではいなかった。師匠は、袈裟の裾のところを指で丸めたり、伸ばしたりを繰り返していた。
「ぐぬぬ。一休や、これは一本取られた。さすがの余も、絵に描かれた屏風を追い出すのは無理じゃ。褒美を取ってつかわすぞ。わははははは。わははははは」
将軍がどういう結論を想定していたのか。依然、謎に包まれている。
一休は、価値観・信念をこの出来事で固めた。もう絶対にこの俺は自分自身しか信用しない、と。
—
それからは史実で伝えられているように、一休は”破戒僧”として生涯をまっとうした。酒を飲み、肉食をし、女を抱きまくった。虎の件があってから、周りの人間を信用してはならず、信じる者すなわち己のみであるとの考え方を貫いた結果、めちゃくちゃやりまくったのである。めちゃくちゃやりまくる坊主の生き様は、市井の人々の賞賛を呼んだ。臨終の間際、一休は「死にとうない」と呟いたと伝えられる。ほとんどの人間がぽっくり死んでいき、成仏を願っていた世の中にあって、この世に未練を抱くこと自体が一部の上流階級の特権でもあった、のかもしれない。享年八十七歳。

 JET
JET




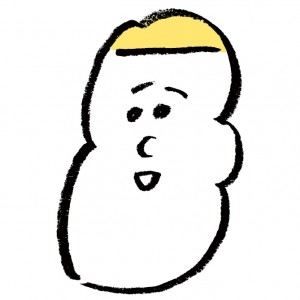 小山健
小山健
 JUNERAY
JUNERAY
 BIGSUN
BIGSUN
 雨穴
雨穴
 梨
梨







