7月の文化祭に向けて1ヶ月を切り、校内は浮ついた雰囲気で充満しているのかと思いきや、昨年初頭から水際で食い止められなかった「恐れのある」とされる未知のウイルス・病原体の影響で中止になるかもしれないという噂で持ちきりであった。ヒトに感染する事例があったわけではないらしいけれど、ある港町では、道端に倒れていた野良猫がむくりと起き上がり、男性を襲った事件があった。
「総理、ひょっとするとひょっとする、なんて言い方はアレですけれども、もしかしたらゾンビ・ウイルスなのではないでしょうか?死者が蘇るみたいな。」
「いい加減にしろ。アタマがどうかしてしまっているのか。映画やマンガじゃあないんだから。帰ります。あとは私の個人チャンネルで全てお話ししますから。サブチャンネルではDIYで、いろいろな食材をくん製したりもしていますから。よろしくお願いします。」
一切の海の向こうの情報がわからない。
わたしの祖母の時代に、どこからか風に舞ってやってきたばい菌のせいで、卒業旅行でオーストラリアに行く予定だったのが中止になったらしく、結局この年まで海外旅行に行けていない、死ぬまで恨み続けるつもりであると冗談まじりに話していた。海外に出かけるなんてまったくの絵空事になった今となっては遠い過去の出来事でわたしには関係のないように感じていたけれど、とにかく家に引っ込んでおいたほうが得策なんじゃない?文化祭なんかやってる場合なの?あそこの学校もやめるらしいよ?という雰囲気が周囲に立ち込めるにつれ、祖母の悪態を思い出さずにはいられないのだった。
高校三年生の夏を心の底から待ち望んでいたかといえばいまいちそういう訳でもなく、美術部の展示といえば、仲の良い子が顔出しに数名現れるくらいのもので基本座っているだけで暇である。気合を入れてパンフを配ろうなんて下級生からの意見もあったけれど、「やる気がない」「いい加減にしろ」「下っ腹が痛い気がする」などの適当な理由をつけて逃げ切った。だったらそもそも展示なんか出すなと思われるかもしれないが、部活動である以上は「活動」している様を形にして示せよとのお達しが学校から出ている以上、しぶしぶ、である。わたしは正面から見たハシビロコウの模写を展示することに決めた。睨みつける視線で人が寄り付かなくて良いだろうと考えたのである。
クラスではポップコーンの屋台をやるそうだ。何種類かのフルーツフレーバーを用意するらしい。わたしは間違いなくしょうゆバター味が一番美味しいと確信してやまないからまたここにも溝がある。いちいちケチをつけたい訳じゃないはずなのに、少しでも「なんか違うな」と感じるだけで距離感を置いてしまうのである。しょうゆバター味のポップコーンを食べながら家でカンフー映画を観ていたほうが楽しいんだからしょうがない。大勢で騒ぐよりも、数人の気が合う友だちといるほうがいい。機械はレンタルで、包装を自由にデザインできるという。クラス名「3ーA」と、「Ever Friends」とメッセージが入るらしい。果たしてそうか?
—
ハシビロコウのスケッチを描きに、週末わたしは電車で1時間ほど揺られて動物園へ出かけた。梅雨明けしたばかり、直射日光がきつく、入念に日焼け止めを塗る。芸大が近いこともあって、同じようにスケッチブックを広げている学生たちの姿がそこかしこに見られる。ハシビロコウの前は思いのほか人が多かった。じっと動かないし描きやすいのだろう。横の檻にいる「ニシムラサキエボシドリ」にしようかな、原色でキレイだし、とも思ったがここは初志を貫きハシビロコウで行くことにした。スケッチバインダーを広げる。強制されるのは億劫なのだけれど、描くこと自体は案外好きだ。しゃべるよりもしゃべれるような気がする。どういう意味かはまとまっていない。
何してんの?と聞こえた。何ってハシビロコウのスケッチですよ。見たらわかるだろ。気のせいと思い無視した。また聞こえた。さすがに振り返った。
「何してんの?」
「え、ス、スケッチです。あ」
「よ」
同じクラスの汐見くんだ。向こうも1人のようである。
「そういえば美術部だったっけ?」
「うん。文化祭で出さないといけないから」
「意外と熱心にやってるんだ」
「ま、まあ」
「ちょっと見せてよ」
「あ」
拒否する間もなく、こちらを睨みつける一切の可愛げのないハシビロコウを覗き込まれた。やめてほしい。
「うまいねえ、さすが美術部。やる気ないのかと思ってた」
普段どれだけ覇気がないと思われているのか。普段学校で生きているのか?わたしは?陽炎(かげろう)か?
「あ、ありがとう。汐見くんはなんで来たの?」
「なんでっていうか、動物好きなんだよ。もう、リアルの動物が見られる場所なんか動物園ぐらいしかないから、時々来る。」
「そうなんだ」
サッカー部だった。確か。彼は。「サッカー部なのに意外だね」とでも返そうとしたのだけれど、「サッカー部なのに」「1人で」「動物園に来るのが意外」はわたしの偏見であって、それをすぐに伝えるのも失礼だし、そうは言っても他に二の句を継ぐフレーズが思い浮かばず、へらへらしているのが関の山で、汗だくで鳥を模写する奇妙な女、以上でも以下でもなくわたしは表情と裏腹に心の中で泣いていた。汐見くんは陽によく灼けていて、正面から見てわかるほど僧帽筋がしっかりしていた。にこやかに笑う、という行為と、へらへら、は近しいようでまるでかけ離れた印象を与えうる、または与えられうるものだと思った。二重に太陽が直列しているように錯覚した。天体すご。
「でも、そんなにうまいんだったら屋台の立て看板とか描いてよ。人いないし」
「え、嫌だ」
「はっきり言うなよ。今日どうするの?これから」
「どうって、帰るけど」
「飯行った?」
「まだ」
「じゃあ、行く?スケッチ終わったら」
終わってなかったのだけれど、待たせるのも申し訳がないからバインダーを畳んだ。道具一式をリュックサックにしまい、パンダの背後を抜け、うつぶせのホッキョクグマを見物、コビトカバ意外とでかい。
わたしは汐見くんと園外のレストランに入った。来月の文化祭のこと、月に1度は動物園を訪れること、両親ともに病院勤務だがお医者さんではないらしいこと、妹がアイドルのオーディションを受けようとしていることなどを知った。わたしは聞いているばかりで、極力会話をさまたげないように努めた。300グラムのハンバーグを美味しそうに食べていた。バイトしてるし、誘った側だからと料金をまとめて支払ってくれた。わたしは、最寄駅から自宅までの帰り道を蛇行しながら帰った。熱が出た。ポカリスエットを飲んで寝た。


 JET
JET


 梨
梨
 加味條
加味條
 エマゴー
エマゴー

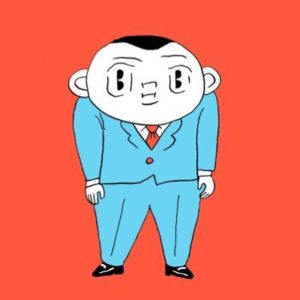 サレンダー橋本
サレンダー橋本







