世の中には、お互いになあなあで、喋っている内容を理解したつもりになったまま、雰囲気だけで進んでいく会話が多いものである。学校だったり、バイト先だったり、職場だったり、ふんふんと相槌をうち、その場の時だけが過ぎゆくのだが、実質何も喋っていない。
「ねえ、あの時のあれって上手いこと進んでるんだっけ?」
「ああ、あれですか。順調ですよ。話通しておいたんで、問題ないです」
「それなら良かった。基本的に任せておくから。何かあったら連絡してね」
「OKです。お疲れ様です」
特に成されたところで一つも事態は前に進んでいないこのようなやり取りを、長く生きていればそれだけ経験しているだろう。「あれ」の指す中身がお互いにずれているケースもあって、積もり積もって大事を招くなんて事態にもなりかねないのだが、ファジーなコミュニケーションを、社会との摩擦・軋轢に苦しまないようにひとつの処世術として使いこなしている人も多い。意図的にせよ、そうでないにせよ。
—-
室町時代、一休という坊主がいた。
ぼやけたようなぬるま湯の湿気に満ちた昼下がりの出来事だった。呆けたような面をぶら下げて、師匠にあたる禅僧が叫んだ。「一休!一休や!」と。一休は、とっくにこの爺さんをあらゆる面で「超えている」と認識していたので、「人の名前を大声で呼ぶな。この暑い日に。蝉の声もギャンギャンうるさいのに。爺さんの声が重なり合って尚更やかましい。馬鹿が。せめて涼しい日に呼べ。涼しい日の夕暮れ時に呼べ」と拳を床に突きつけたが、とりあえず、一応、いきなり牙を向いても爺さんが泡を吹いてぶっ倒れるだけで面倒臭くなるだけなので、「はいはい。なんでございましょう、お師匠さま」と返した。
「一休や。将軍様が、お前に用事があって、城に遣わすと仰っておる。先ほど使いの方がいらっしゃって、お前の知恵を借りたいと」
「なんでですか?なんかあったんすか」
「うーむ。仔細は聞いておらぬのじゃが」
仔細をなぜ聞かないのか。この歳になって、「ただもらってきた話を、伝えるだけであります」との伝令ムーブにいささかの疑問を抱かないのか。少しは自分の頭で考えて、自分の意思でこの世を良くしようとか、考えてくれよ。頼む。本当に。と頭を痛めたが、師匠も師匠で、「試練をこやつに与えて、成長させてみよかな。ワハハ。ソモサンセッパ」と無責任極まる根拠のもとに行動していた。
成長もくそも、一休が今回の出来事をどう捉えるかによりけりであって、一介のじじいがハンドリングできる筋合いの話じゃないのだけれども、「周囲と比較して長生きをしているから、自分の忠告は年少の人間の糧となるだろう」と、「生きている」ことがステイタスの時代であったので、偶然、運良く生きていた師匠がほいほいと、「自分は君の何倍も生きていますよ」と潜在意識下で居丈高に振る舞うことに一休は憤っていた。
「お師匠様。本当になにも聞いていらっしゃらないのですか?」
「聞いておらぬよ。だって、相手は将軍様だから。変に勘繰ったところで、こちらが怒られてしまう可能性があるわけだから。なるべく怒られたくはないわけだから」
「えっ。怒られたくないんですか。お師匠様。失礼ながら、おいくつになられるのでしょうか」
「七十八(しちじゅうはち)」
「まだ、怒られたくありませんか」
「……うむ」
「もう、なんていうんですか。もう少し偉そうに振る舞ったっていいと思いますよ。お立場だってそれなりに上でいらっしゃるわけですから」
「……言えてる」
「言えてる。じゃなくて。今だって”それなり”って私、ものすごく失礼な物言いしてますよ。ズドンと叱ってくださいよ。昔水飴の件あったじゃないですか。あの時だって私、正直ぶん殴られるの覚悟してましたからね」
水飴の件とは、師匠が「毒」と偽って隠していた水飴を、一休が他の坊主どもと結託し、「ミスをやらかしてしまったので毒を食らって死のうとしました」と舐め尽くした、というエピソードである。師匠も師匠なら弟子も弟子で、互いに騙し合い・化かし合いを繰り返し、いつも一休が師匠を上回っていたところ、以上のような主従関係の逆転が生まれてしまったのである。
「で、行ってくればいいんですか?城に」
「うむ。そうしてもらえるとだいぶ助かるのであるが」
「助かるって誰がですか?師匠がですか?なぜ私が師匠を助けなければならないのですか?あなたの弟子だからですか?なんでですか?なんでですか?なんでですか?」
一休は、周囲のいい加減な大人が許せなかった。しかし小柄で腕っ節も弱かったため、口八丁で相手をやり込めるのだった。周りに居てほしくないタイプとも言えるが、目上の人間に物おじせず、市井の評判は良かった。
一休自身、やんごとなき家柄の隠し子であった、という複雑な出自で、幼少のころから「周囲は信じられない。いつ死ぬとも限らないから、言いたい放題・やりたい放題やってこの世を謳歌し尽くしてから死んだほうが得なのではないか」と考えていた。
「すまぬ。色々と納得いかないことも多かろうが、チャンスみたいなものと思って。私も付いていくし」
「だからチャンスって……」
もう埒があかん。行くだけ行ってやるか。なんだか知らんが。一休は支度を始めた。
—
京都の夏は暑い。一休の勤めていた寺から屋敷まではだいたい歩いて25分ぐらいであったが、蝉の声さえも壁にへばりつくような湿気に塗れながら、一休は、「マジで気が利かないな。馬鹿くそ暑い時期に客を呼び寄せますかね。まあ、この世で一番偉いんだからしょうがないんだけど」と独りごちた。盆地に溜まった湿気と、歩いて25分という絶妙にだるい距離が相まって、「ああ、その辺に腰掛けて、氷を舐めたり、柑橘類を齧ったりしたいなあ。なんでこの世で一番偉いおじさんに会う予定が入ったのだろう、なめんな。マジで」と重ね重ねぐちぐち呟きながら、うねうねと曲がりくねり屋敷に向かった。
随行している師匠が「ああ、暑いのお」と漏らした。一休は知っている。知っている。そんなことは。いま、目に写っている誰もが同じ感想を抱いているのだから、喋らなくてもいい。話題にすんな」と斜め下を向きながら歩いていると、小川に架かった橋の前に立てかかっている看板の文言が目に入った。傍には、見張りに勤めているやる気のなさそうな中年男がいる。
『このはし、渡るべからず』
「おお、一休。工事中か?今この橋は渡ってはいけないらしい。回り道をしよう」
しかし、一休は幾許かの違和感を覚えた。そのような普請の最中である形跡・様子もないし、橋自体が傷んでいるわけでもなさそうである。なのにも関わらず、つい最近立てられただろう「このはし、渡るべからず」の看板。一体なんだろうか。
まさか、「はし」がひらがな表記だから、”橋”と”端”がかかっていて、真ん中を渡れば正解である。なんて知恵試しであるとしたら。時の将軍ほどの権力を持っている人間が、この程度の「とっておき!だじゃれなぞなぞ100」レベルの嫌がらせ行為に走るだろうか?むしろ、「真ん中を渡れば正解」という正しい道筋を裏切ってこそなのではないだろうか。
あえて端っこを渡ったらどうなるのか?たぶんそれが「私の心に従った正解」で、相手の嫌がらせの方向性を読み切って橋の端っこを渡る。あるいは、師匠に従って回り道をする……。いや。だめだ。真ん中を渡ろう。この見張りがおそらく将軍と繋がっていて、私が「橋の真ん中」を渡った場合、「正しい行動を取った」と報告するであろう。からの、あっぱれじゃ。である。
もう、知らんからと端っこを歩いてしまったところで、将軍にここまでの「思考の道筋」を説明するのが億劫である。「全部わかっていてお前をなめていたからですよ」と説明するのと同義で、師匠も私もしばかれる。というか、最悪殺される。それに、回り道をすればかなりの時間をロスする。将軍のアポに遅刻するのももってのほかだろう。いろいろと腑に落ちないが、一休は真ん中を歩いて橋を渡ることにした。
「師匠。真ん中を渡りましょう。真ん中」
「え、なんで?」
「あの、おそらくですけれども、”このはし渡るべからず”つまり、”端っこ”を渡ってはいけないという意味ではないでしょうか。だから、端ではなく真ん中を歩けばいいのですよ。さあ、行きましょう」
「一休、ま、待ちなさい。危ないぞ」
一休は堂々と橋の真ん中を歩いた。見張りの男はぼさっと突っ立っているのみであった。蝉がじりじりと鳴いていた。容赦のない日差しが降り注いだ。橋は崩れ落ちもせず、向こう岸に渡ることができた。
「お主の言う通りじゃったな、一休。屋敷へと急ごう」
何も言うまい。一休は振り返りもせずに歩みを進めた。
—
「よくぞ参られた。そちが一休か。評判は余の耳にも届いておる」
謁見の間に通された一休と師匠は、うやうやしくぬかずいて将軍・足利義満の挨拶を聞いていた。
「面を上げるがいい」
一休は、「”橋”と”端”をかけただじゃれを考えたのはこの男か。しかもこの世で一番偉いのか。楽しくてしょうがないだろうな。人生。眉毛細いな」と思ったが、そんな様子はおくびにも出さずにとりあえず神妙な面持ちで話を聞いていた。
「暑かっただろう。茶屋の方ではそろそろ鮎が出る頃だろうか」
「……。」
師匠は押し黙っている。明らかに緊張している。
何かしゃべってくれ。今は師匠の番だ、絶対に。少なくともアイスブレイクはあなたの役割なんじゃないのか。
「……。」
しびれを切らした一休が会話を切り返した。
「はい。桂川の鮎が出回っているようです。もっとも、本来我々はなまぐさものに手をつけられるような立場ではございませんので、あくまで町の風情として楽しむにとどまっておりますが」
「そうかそうか、あとで食事も用意しているから、楽しんでいくがいい。ところで、道中の橋の罠。あれは実は余が用意をしていたのだが、いとも簡単に見破ったそうであるな。流石じゃ」
「ええ、まあ」
やはりか。舐めんな。一休は思った。
「さて、そちを招いたのには訳があってな」
将軍はひとつ咳払いをし、本題に入った。
「お主の知恵を借り、ここに解決して欲しい問題がある」
と切り出すやいなや、将軍は立ち上がり、下々の者が幕に覆われた何かを運んできた。それは将軍の腰の高さほどはあっただろうか。ワイドが1,400mm、奥行きが600mm程度の、一般的な1人用OAデスクの平板程度はありそうなサイズ感の物体であった。
幕が降ろされると、凶暴な目つきで、竹林の隙間からこちらを睨みつけている虎の屏風が現れた。今にも飛びかかってきそうな剣幕の、小さな子どもが見れば震え上がって泣き出しそうな代物であった。
「一休よ。この虎が、毎晩屏風から抜け出し、悪事をはたらくのでほとほと困り果てておるのだ。頼むから、この虎を退治してくれるわけにはいかないか」
将軍は、どうだ、お前を困らせてやろう。さてさて、どう切り返す?とんちの得意なお前は?とでも言いたげに一休を見やった。
—
一休は、「は?」と思った。
何を言っているのかまったくわからなかった。
周囲の家来たちも、「一休、さぞや困っているに違いない。なにがとんちだ。小僧が」との雰囲気ありありなにやけた表情を浮かべていた。
絵から虎が飛び出すわけもなくて、それは考えるまでもなくそうなのであるけれども、うまいこと切り返す手段がそもそも存在するのだろうか。とか、「は?意味がわからないんですが」と返事するのも一瞬脳裏をかすめたが、たぶん我々は死ぬ。死ぬが、なんていうか、コミュニケーションを適当に取ればこの場をやり過ごせるのだろうか。この眉の細い壮年男性の機嫌を損ねないように振る舞えばよいのか。しかしそれもそれで腹が立つ。いや。これは人生の岐路だ。一休、考えろ。二つに一つ。こいつら、揃いも揃って馬鹿しかいないのか。夏だ。暑い。玉露が飲みたい。アイスで。
一休は答えた。
A「かしこまりました。それでは、将軍様。この虎を締め上げるための丈夫な縄をご用意ください」

 JET
JET




 BIGSUN
BIGSUN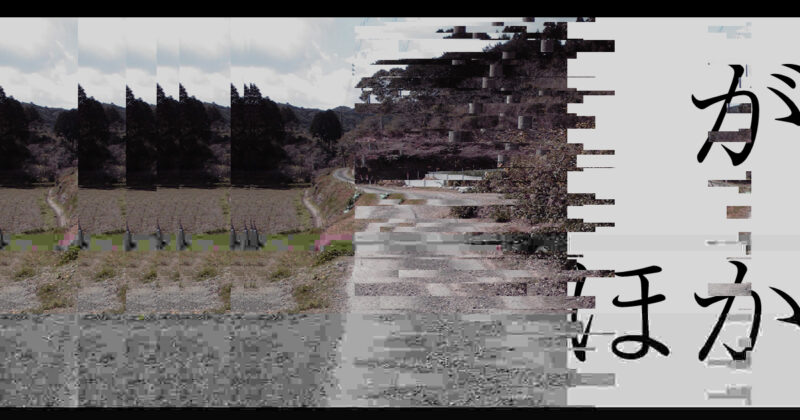
 梨
梨
 エマゴー
エマゴー
 城戸
城戸
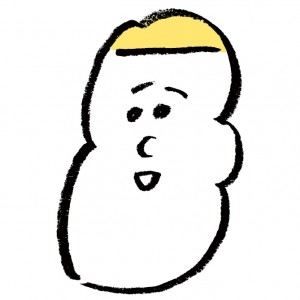 小山健
小山健







