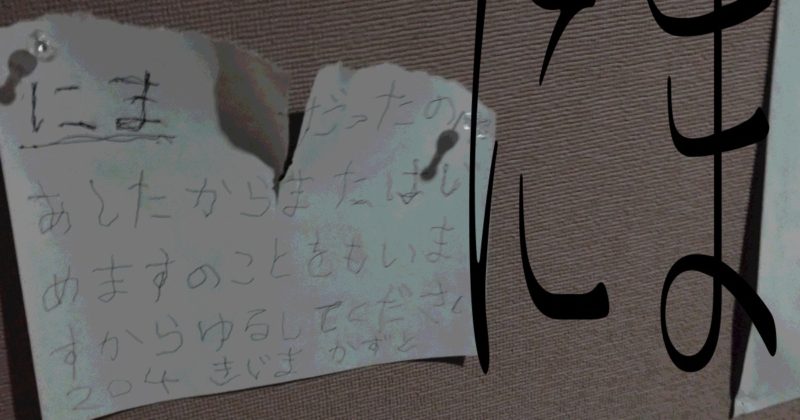猛烈な喉の渇きと頭痛で太郎は目覚めた。赤ワインの澱(おり)が頭の皮の裏にこびりついているようだ。太郎は昨日たらふく呑んだそれが「赤ワイン」であることなんか知る由もなかったが。
「気持ちが悪い。気持ちが悪すぎる。水飲ましてくれ。乙姫ー。アー」
とうつろに周囲を見渡すと、昨日暴食・鯨飲しまくったあのビカビカの部屋ではなくて、一度も張り替えられていないような四畳半に寝転んでいた。ちゃぶ台の足が見えた。状況が理解できず混乱していると、誰かがふすまを乱暴に開けた。
「いつまで寝ているんだ。さっさと起きろ」
「うるせー。いつまでって言われても知らねーよ。鐘でも数えてろよ。ていうか、乙姫は?なんか今度、箱根?に行く約束したんだけど」
「馬鹿かお前は。誰に口を利いてるんだ」
太郎よりふた周りも体格の良い、髪を蝋で固めたかのような全身黒づくめの男が立っていた。威圧的な容貌は、三次を思い出させた。
「会計だよ会計。さっさと支払え」
「は?会計?」
「勘定だって言ってるんだよ。カネだよカネ」
「カネ?ああ、銭。あるわけないじゃんそんなの」
「何?お前、無一文で飲食したの?犯罪だよ。それ」
「うーん。何言ってるか全然わからないよ。素寒貧(すかんぴん)に決まってるじゃん。だって俺、亀に連れてこられてもてなしてもらったんだもん。銭なんか持ってきてないよ。もう済んだんなら家に帰りたいよ。あ、箱根?に行かないと。亀呼んできてよ」
「馬鹿も休み休み言え。耳揃えてカネを払ってもらうまでお前を家に返すわけにはいかないんだよ」
黒づくめの男は、薄い板のようなものに貼られた細長い紙きれを太郎に押しつけた。太郎は文字が読めなかったが、マル印がずらーっと並んでいるのだけは辛うじて認識できた。
「いくらなの?これ。帰って母ちゃんに頭下げたら多少は工面できるかもしれないけど。そもそもなんで銭がかかるんだよ」
「飲み食いしたからだろうが。オンナまで呼んで」
「だから頼んでないんだって」
「とにかく支払ってもらう必要があるんだよ。お前の時代で言えば、村中の牛を売り捌いたって足りないが」
「時代?牛?いいから早く返してくれ」
「だめだ。お前には支払う義務がある。これを見ろ」
男はふところから、写真と、また別の紙切れを出した。
「誰?この阿呆丸出しの締まりの悪い男は」
「お前だよ。太郎」
「これが?」
太郎は首をくくりたくなった。焼けた土くれみたいななりをしていた。てんで目の焦点が合っていない太郎が、親指に朱を塗りたくられ、細々と文字の書かれた紙きれに指を捺しつけている。太郎には憶えがない光景だった。
「動かぬ証拠ってわけだ。文字の読めないお前に教えてやるが、ここにはお前が支払いを終えるまで竜宮城から一歩たりとも外に出ることを禁ずると書かれているんだよ。わかったらさっさと諦めて働け。死ぬ気で働け。或いは死ぬまで働け」
「は?訳がわからん。助けてくれ。俺が何したってんだ」
「諦めろ。理由があるとするならば、お前が”何もしていないのが悪い”んだ。あ、ちなみにこの部屋にお前は住んでもらうから。一人部屋だぞ。感謝しろよ」
「ちょちょちょちょちょちょちょちょちょちょ。ちょちょちょちょちょちょ」
男は太郎の制止を振り払い、部屋を去った。
太郎はつくねんとした。ひとりで。
—-
十坪の売店には、蜜柑味のサイダー、冨岡義勇のはっぴ、なぞなぞが百個載っているキーホルダー、「NYAIKI」のパーカー、鳥獣戯画の扇子、金箔入りの日本酒、チョコラングドシャ、柿渋のボディソープ、黒炭のボディソープ、馬油のボディソープ、Kiroroの『ベストフレンド』が流れるオルゴール、十二支をモチーフにした蜻蛉玉、海老煎餅、酒粕配合の5枚入りフェイスパック、「竜宮城」ロゴのマグネット、浴衣を着ているハローキティのハンカチ、札束みたいなメモ帳、カニのハサミ型のライター、ちょっといいぽん酢、地元の水産高校生が監修したレトルトカレー、等が売られていた。
客はぐるりと店内を一瞥したのちに、いくつかの商品を手にとって眺めたものの、何も購入せずに店を去っていった。
「ったく、どいつもこいつも冷やかしばっかりじゃねえか」
「まあ、愚痴るなよ太郎くん」
太郎は制服を着用し、レジスターに立っていた。珊瑚を模したピンバッジが襟元で光っていた。店内には同じ制服を着用した、白髪の目立つ初老の男が品出しをしていた。
「来る日も来る日も、俺たちはいつまでこんな意味のないことやらなくちゃいけないの?おっさん」
「いつまでってそりゃ、死ぬまでだよ。前も答えただろう」
「ほとんど誰もなにも買わないし。何のためにやらなくちゃならないんだ?品出しやめたら?」
「何のためってそりゃ、働けと言われているからだよ。品出しをやめたら怒られちゃうだろ」
「働けと言われているから、働かなくちゃいけないの?」
「働けと言われているから、働かなくてはならないんだよ」
「怒られたくないから品出しをしてるの?」
「怒られたくないから品出しをしてるよ」
「ちょっと待ってくれおっさん。おっさんは疑問を感じないのか?」
「疑問を感じないようにするのも生きるコツだよ」
「もっとこう、あるだろ。俺だって昔は浜辺で蟹を棒で突いたり、海苔をこそげたり、まあ意味はなかったかもしれないけれども、それは自分の都合のためにやっていたのであって、けっこう楽しかったしそれなりに愉快だったよ。でも、おんなじ意味のなさでも、強制的に押しつけられる意味のなさに俺はどうしても耐えられないよ。俺は村に帰りたい。家で大の字になって寝たい」
「違うなあ。太郎くんと僕は。僕は同じ意味なく生きるなら、押しつけられたほうが楽でいいな。考えなくていいから。住み込みだから、いちおう最低限の食いぶちと寝床は保証されてるんだし。でさ、そうは文句を言っても、何ヶ月かに一回は馬油のボディソープが売れることもあるわけじゃない。そうしたら、僕が補充しなくちゃいつかは売り切れてしまうだろう。必要とされているじゃないか」
「いや、おっさんじゃなくてもいいだろう。その仕事は。馬油のボディソープを補充する人生で終わるんだぞ?」
「まあ、考えなくていいから楽だよ。時間も早く過ぎ去るしね」
話にならん。太郎は憤慨した。
三月前に竜宮城の土産売り場に配属されて、おっさんと組んだ。おっさんはもう数十年この売り場で勤めていて、代わり映えのない日々を送っていたのだが、太郎という話し相手ができて少しだけ嬉しいようであった。太郎は、おっさんから手ほどきを受け、商品の名前や用途を一通り覚えた。
おっさんから聞かされたのであるが、この「竜宮城」はありとあらゆる時代から日頃なにも産み出していない選りすぐりの無能を収容し、強制的に勤労させることで経営が成り立っている一大娯楽施設だということだった。おっさんは、太郎の過ごしていた時代よりも八百年ほど先の「令和」の世から選別された無能で、役場のパソコンでソリティアに勤しむ日々を送っていた。ある金曜日に、安居酒屋で安日本酒を飲んだ帰りの路線バスで寝過ごし車庫まで辿り着いてしまい、暗闇を彷徨っていたところいつの間にか竜宮城の明かりを目指していたらしい。そこから先の顛末は太郎と以下同文である。
そして、結局亀と三次たちはグルだったわけだ。三次も三次で、案外世に貢献していたのだね。いい勝負のはずだったのにね。と太郎は思った。
生活にはうんざりしていた。来る日も来る日も、売れもしない土産物に囲まれ、時が過ぎ去るのをひたすら待っていた。おっさんは打っても何も響かないぼんくらで、気の利いたことひとつ言わない。この無能と並列とみなされたのか俺は。と怒りすら覚えていた。
どうにかして村に戻る方法を探さなければならない。真面目に働いたとて稼げる銭はわずかで、太郎が飲み食いした代金を返すためには命がいくつあっても足りなかった。もっとも、太郎の時代に「ぼったくり」なんて概念はなかったから、飲食費が適正価格ではないことを太郎は知るはずがなかった。
従業員には、世間の無能を見張り、査定する業務に就いている者がおり、それは太郎のような三下の役目ではなく、目のかけられた幹部候補生たちの仕事であった。毎朝出勤してくるそいつらに頭を下げなくてはならないのも、太郎は苦痛だった。おっさん曰く、「それらは全て、そういうもの」らしかった。
しかし太郎は或る日閃いた。もしかして奴らに成り済まし、勤務する職場に忍び込めたならば、元の世界に帰るあてがあるのではないかと。足りない頭で作戦を立てた。連中は太郎らが立ち入りを禁じられている、仰々しい金属の扉の向こうで仕事をしている。様子を伺うと、連中が首から紐でぶら下げた札のようなものをかざすと扉が開き、部屋に入ることができるようだ。あの札を手に入れ、出口を探そう。連中は毎朝決まった時間に出てくるし、毎晩決まった時間に帰路につく。晩は静まり返っていて、人の気配もない。その間にあの部屋に入ることができれば、好機はあるかもしれない。
「おっさん、あの部屋ってさ。入ったことある?」
「ないよ」
おっさんは使えなかった。頼るほうが愚かであった。
—
長い月日が経った。ような気がするほどに、代わり映えのない日々が続いた。今日も朝からおっさんは鼻歌を陽気に奏でている。幾度ぶん殴ろうかと脳裏をよぎったか知れない。
「ああこれ?涙のキッス。サザンの。知らない?」
知る訳がない。
しかしその日は、城内の雰囲気がどことなくせわしなかった。出勤してくる連中もいつもより機嫌がいいようである。
「太郎ちゃん。頑張ってる?」
「え、ああ、はい。まあ」
「太郎ちゃん」なんて親しげに声をかけられたのも初めての経験であった。そこはかとなく不気味な印象を抱いた。
「おっさん、あれ何?今の」
太郎は質問した。
「確か今日、社員のみんなは忘年会じゃなかったかな。一番でかい部屋を貸し切って、どんちゃん酒を呑むんだよ、無論、我々には関係ない話だけどね。涙のキッス もう一度♫」
ああそうなんだ。いい気なもんだね、しばいたろかと太郎は業務に就こうとしたが、もしかしてついに巡ってきたのじゃない?好機が?と電撃に体を貫かれた。会場に忍び込んで、酔っ払った連中から、誰でもいい、とにかくあの札を奪って、扉を開け、あの部屋に入るのだ。もし計画が失敗し、ひどい罰を受けるか知らんが、おっさんと永遠に・共に過ごすのよりはよっぽどマシだ。太郎は目をぎらつかせながら、浮かれた連中の背中を睨みつけた。
そして夜が訪れた。おっさんは先に自分の部屋に戻った。「あれ、帰らないの?」と少し不審そうに尋ねられたが、「大丈夫す。そういえば今日、クリスタルの竜宮城ウォッチ、一個売れたじゃないですか。補充しときますよ」と適当な理由をつけて店に残った。「妙に熱心だね。いくら働いても給料は変わらないよ」と興を削ぐ忠告を残していった。
さて、ぞくぞくと社員が大広間に集まり出した。太郎はレジスターの陰に身を潜めた。これだけ人数がいれば紛れても目立ちにくいし、給仕のために雇われている太郎と同じ身分の者もある程度の人数が確保されているようだったのも太郎にとって好都合だった。太郎は、酒の回り出した宴の終わりごろを狙おうと決めた。
売店のあるロビーにも、大広間からどんちゃん騒ぎの様子が漏れ聞こえてきた。引き続き固唾を呑んで機会をうかがっていると、
「えー、皆様。続いては、お待ちかねの豪華景品争奪!ビンゴ大会でございます。えー、お手元にビンゴカードは配られておりますでしょうか。ちなみに一等賞はですね、こちらの羽のない扇風機でございます。どういう仕組みで風が出てくるんでしょうか、わたくしには見当もつきません!(場内、笑)みなさま一旦お食事の手を止めてですね、しばしの間お付き合いいただきますようよろしくお願いいたします」
と、酔いの交じったけたたましい音声が聞こえてきた。内容はほとんど太郎には理解できなかったが、とにかく恐ろしく下らないであろうことだけは本能で察知した。
売り場を出て、会場に忍び込んだ。もう宴もたけなわであり、外で給仕に就いている奴らもさっさと部屋に戻りたい欲求で頭の中を埋め尽くされており、太郎を止めようともしなかった。すんなり会場に入り、広間のいちばん奥にある壇上に目をやると、女が花輪を首からさげられ、一言求められているようだった。
「まさか一番で当たっちゃうなんて……。部屋で大事に使おうと思いまーす」
乙姫だった。太郎は壇上まで駆け上がって渾身のフライングニールキックをかましたくなる怒りをぐっと堪えた。おのれのせいで俺は永い間苦痛を味わっていたのだ。箱根?にも行けなかったし。太郎は逆恨み半分であることなどすっかり忘却していた。ちなみに、乙姫はとっくに羽のない扇風機を所有していたので、即日メルカリに出品した。四万八千円で売れた。
ひたすらビールを呑む者、真面目にビンゴの番号が呼ばれるのを待つ者、喫煙しに外に出る者、役員にこびへつらう者、誰かが残した肉団子をむさぼる者、今から寿司の列に並びに行き品切れと告げられる者、尻を触り明日殺される男、尻を触られ明日殺す女など、場内は収集のつかない事態となっていた。太郎はある卓上にあった、かねてから喉から手が出るほど欲しかった「札」を、いともあっさりと入手してしまった。こんな呆気ないものかね、と太郎はやるせなささえ覚えた。
太郎は会場を後にした。誰も後をつけてきている気配はない。そこで太郎は、ついでだから元の時代に戻れた後に都で高く売り捌こうと、売店の珍品を見繕って持ち帰ることにした。家に迷惑もかけていたから、多少は孝行でもしてやろうかという自責の念もないではなかった。なるべく紛失が目立たない品物にしようと、おっさんが売店を任されて以来、一度も売れていない店の「ヌシ」のような存在であると聞かされていた、蒔絵の施された小箱を持ち帰ることに決め、懐にしまった。
あの鉄の扉の前に立った。毎朝頭を下げていた連中の見よう見まねで、扉横の装置に札をかざした。すると、引き戸のようにすべり、扉が開いた。暗がりの中を進むと徐々に目が慣れてきた。
「おい、誰だお前は。今日は忘年会じゃなかったのか?」
太郎は心臓が縮み上がった。声のする方向を見た。
「スタッフだろお前?何でこんなところにいるんだよ」
「いや、なんでっていうか、自分新入りなんで、迷い込んだっていうか」
「新入り?」顔をライトで照らされた。
「お前、売店の店員だろ。太郎だっけ?ちょっと上に報告するから」
二日目に太郎を部屋まで連れ込んだ黒服だった。夜勤で守衛業務に就いていた。黒服も、建物管理会社の派遣であって、何かを成すには一度本社の人間を通すしかないのだった。竜宮城での生活ルールの説明なんかも、守衛業務のうちのひとつであった。黒服は、本社の人間に頭が上がらないストレスを、あらゆる時代から飛ばされてきた無能どもにぶつけて発散していた。しょせん小物であった。ギャンブル中毒で、先日、竜宮城内の競艇にて惜しいところで万舟を外していた。彼は竜宮城で行われる全てのギャンブルが八百長であることを知らなかった。魚卵が大好きで、痛風持ちでもあった。
「おい待て!」
太郎は部屋の中でもっとも「素人が手を出したら上の連中が困るだろう雰囲気を醸している」機械に飛び乗った。
「おそらくこの装置を俺が滅茶苦茶にぶっ壊したら、お前はクビだ、ていうか建物自体どうなるのかはわからん。わかるか」
「わからん。が、とにかく取り返しのつかないことになるんだと思う。早まるな。お前が暴れたら俺の立場がない。そこを動かないでくれ」
「情けないな。なにもわからんままに働いてたのかよ。わかろうと思えよこの野郎。お前に言ってもしょうがないかもしれないけど、俺は帰りたいんだよ。村に。なんとかしないと、俺はここで小便をする」
「ばか。ちょ、ちょっと待て。上を呼ぶから」
黒服はポケットからスマートフォンを取り出し、憔悴しきりで電話をかけた。しばらくすると、よく日に灼けた上背のある男が現れた。社員であることを示すバッジが襟元で輝いている。
「なんだよもー。いい加減にしろよ。人を気安く呼びやがって」
酔いがだいぶ回っているのか、呂律が怪しかった。
「いや実は、太郎の奴が」
太郎はすでに下半身を露出していた。社員は青ざめた。
「おい、何やってるんだお前」
「今からこのお前たちにとって大事な機械に小便をひっかけるから、困るんだったら俺を村に帰してくれ。そうしたら小便は然るべき場所でやる」
その機械は、空間・時間と竜宮城を繋ぎ止めるために必要な安定装置だった。そんな大事なものを剥き出しに置いている時点でセキュリティ対策が甘々であると露呈しているようなものであったが、立地の特殊さや上部層の慢心、「無能」の酷使にリスクを感じていなった爪の甘さから、防御にカネを使うぐらいなら攻撃に全振りせよと宣伝費用につぎ込みまくっていたせいでガバガバであった。管理部門はクラウド化を口を酸っぱくして申告していたのだが、まったく聞き入れられなかった。駆けつけた社員も自分の立場を守るので精一杯だったから、杜撰な管理体制を指摘されないようミスをもみ消すので必死だった。
「わかった。お前を元の時代に帰してやる。名前と出身を言え」
「太郎だよ。浦島の」
—
太郎は故郷の村に帰ってきた。亀も亀で無数にいるようで、どついてやろうと帰り道に息巻いていたが、送迎担当の亀が
「その亀と私は別だと思います。たぶん拾ってくる側だから、アカウミガメでしょ。私は帰す側なんでアオウミガメなんです。普段は敷地内の周遊やってるんですけどね。お兄さんが帰るっていうんで任されたんですよ。いや、初めてですよこんな遠くまでお客さん乗せるの。わくわくするなぁ」
と興味もなく感慨に耽り出したので、真正面を睨みつけながらひたすらに無視を貫いた。
漁にでも出ているのだろうか、実家は留守であった。掃除の行き届いていない様子で、土間の埃が積もっている。なんだよ、せっかく久しぶりに家に帰ってきてやったのに。と太郎は布団に寝転がり、お、そういえば売店から盗んできたあれ、なんだったんだろう。値打ちものだといいなあ。と懐から小箱を取り出して、金具を外し、蓋を開けた。Kiroroの『長い間』が流れてきて、白檀の匂いと白煙が立ち上った。太郎は、心が落ち着く旋律だなあ、とまどろみながら、まろやかな春の日差しに包まれ、睡りについた。


 JET
JET





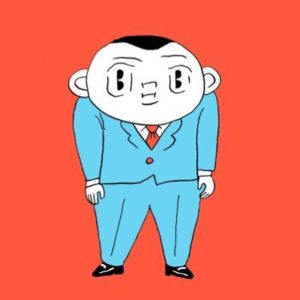 サレンダー橋本
サレンダー橋本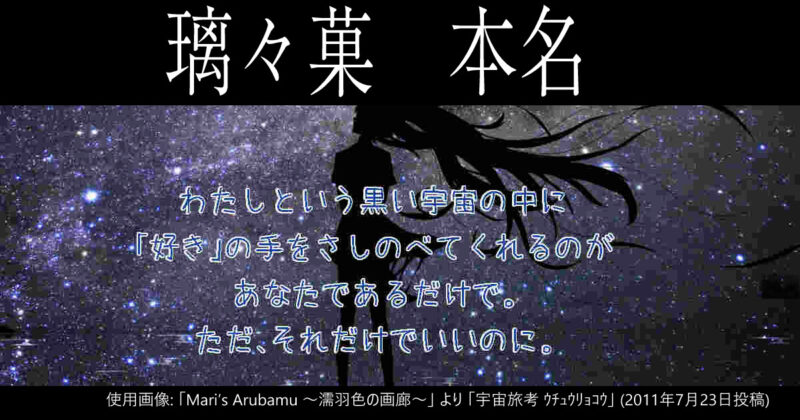
 梨
梨
 金輪財 雑魚
金輪財 雑魚