“好きな服を着てるだけ 悪いことしてないよ”と、私の若い頃に流行歌で歌われていた。が、実際は果たしてそうだろうか。街中で、明らかに壮年の域にまで達している男性が、ツインテールのかつらを被り、セーラー服を着用して悠然と歩いているのを見かけたとしたら。眉を顰めずに、あるいは、一瞥もくれずに横を通り過ぎる自信があなたにはあるだろうか。
その男性は、案外、「そういうもの」「あたりまえ」として街に溶け込んでおり、すれ違う人々が悲鳴を上げるでもなく、警察に詰められているでもなく、風景の一部と化しているようでもある。が、しかし、その男性も街の1ピースとして組み込まれるまでには時間を要しただろうし、流石に「デビュー」の当日は一悶着あったのではないだろうか。
法的手段を取って彼らを排除することはできない。なぜなら「悪いこと」をしていないからである。我々の奥底に湧き上がる「ヒェーッ」「きもい」「あっち行っとこか」などの嫌悪感を抱いたとしても、危害を加えられたとはみなされないのである。そのあたりの線引きについて、たとえば局部を露出したのとはどう違うのか。といった罰と自由の線引きの観点については、まったく門外漢であるのでここでは語らない。私はつまり何が語りたいのかと言えば、40代半ばを過ぎ、男性がパステル・パープル色で全身を固めた場合に、周囲から一体どのような印象を抱かれるか。
むろん「おげげ」「今日は台無しだよ」「もう、帰ります」と、マイナスの感情を抱かれてしまうのが関の山であるのは重々承知の上で、しかも、私のパステル・パープル姿にやる気を削がれて職場を欠勤する人間が現れた場合に、日本国の経済活動に悪影響を及ぼすし、そう考えると、「好きな服を着てるだけ」の状態がやはりネガティブの要因になってしまうわけで、そうすれば、じゃあ好き勝手やられないから、私がECサイトで購入したパステル・パープルのワンピースが布きれの筒になるのである。着用不可能な布きれの筒が、クローゼットの奥底で眠ることになる。
「男性ならば男性らしい趣味趣向・ファッション・ふるまいを」「女性ならば以下同文」との風潮を打破しようとする動きがあって、次第に、世間もその方面になびいていくのが是であると理解はしているつもりだが、人類皆がそれぞれの「自由なふるまい」に心の底から疑問や違和感を抱かないような時代が訪れるのはまだまだ未来の話だろう。
そうだ。私の手元には、今「パステル・パープルのワンピース」があるのだ。どうしてこんなことになってしまったのだろう。着ようとしたからだ。かわいいと感じたからだ。なんなら、”Kawaii”とすら感じたからだ。娘がリビングに置いていた10代後半の女性向けファッション誌を「こんなの読んでるんだな」程度に何の気なしでふと、めくっていたら目についた服装が、私の心臓を貫いたのだった。
当然「なあなあ。たまたまお前の雑誌を失敬してめくっていたのだけれど、いいねえ、この格好」と娘に話しかけようものなら八つ裂きでは済まされないだろう。高校2年生の娘との親子関係は良好とは言えず、いわゆる「年頃の娘を持つ娘と父親」との月並みな関係性なのだろう。
「パステル・パープルのワンピース」を着用したい気持ち、これは「欲情」ないしは「劣情」と呼ぶべきものなのだろうか?もっと純粋な「カワイくなりたい」に近いと考えているが、その感情をいまさら処理すべくもなくて、とりあえず手元に置いておこうと、決して娘にはバレないように「パステル・パープルのワンピース」を購入したのだった。
現実的な問題としてまず挙げられるのは、個体たる私自身が「カワイくない」ことだ。「カワイいという概念からもっともかけ離れた存在」と表現して差し支えない。カワイさと私とは、いわば項羽と劉邦だ。まず出てくる喩えがいっさいカワイくないじゃないか。マイ・メロディとクロミちゃんだ。合ってるのか。これは。
と、私がカワイくなる上で、今、目の前にある現実とのギャップを洗った際にまず解消せねばならないのは、頭皮の裏側や腹囲周りにこびりついた「脂肪」を削り取ることだと考えた。世のカワイい存在たちは過剰な油分を含んでいないのである。余計なことは考えないし、必要なエネルギーのみで動く、美しい存在であるのだ。
—
「あれ、最近アゴのまわり、ほっそりしたんじゃありませんか?」
「ああ、そうかな。最近ダイエットしてるから。病気とかじゃないからね笑 安心してね笑」
と同じ部署で働く年下の女性に指摘をされたのは、上記の気づきから3か月経過したころであった。
妻が勤務前日にこしらえた、油分を多量に含んだ冷凍食品の揚げ物の弁当を公園に捨て、代わりに炭酸水で腹を膨らませ、満腹感をごまかす日常を繰り返すところから始まった。妻には「お弁当、作らなくてもいいから」と一言伝えるだけでよかったのだが、なぜ?と問われた際に「カワイくなりたいから」と言い出せなかった。ちょっと健康に気を遣って、とか適当な言い訳が不自然に感じた。カワイくなるためには自分のために純粋に真っ直ぐ生きていかねばならないのだ。午後はお腹が空きすぎて眩暈がする。
通勤途中には、スマホに有線のイヤホンを挿しNHKのラジオ放送を聴いているが、まず有線イヤホンの使用をやめ、パステル・パープル色のヘッドホンを被り、「ボーカロイド」が歌う早いし高いし何を言っているのかまったくわからない歌を聴くことにした。人間は加齢により可聴域がだんだん狭まるというが、そのせいもあるのだろうか。歌詞を検索すると、「浮気症の彼氏の首を絞めて殺害する」とか物騒なことを喚いているようだ。あまり物々しい話はせずに熱い味噌汁でも飲んで落ち着いてほしいところだが、彼女らは味噌汁なんか飲まないだろう。
私は普段はあまり寄らないスターバックスに通い、季節の甘いものを摂ることもはじめた。10月中旬は”焼き芋味の甘いやつ”だった。頭脳がとろけるほど糖が効いていて、身体が若返っていく。こんなもの常飲していたら太るに決まっているのだが、”流行の甘いやつ”を摂取することと”痩せていること”を両立しなければならず、矛盾を孕んで生きていく必要があるのだ。カワイくいるためには。
本来はスーツなんか着用したくはないのだが、流石にパステル・パープル色で通勤をするわけにもいかないので、せめてもの抵抗でネクタイをパステル・パープル色にした。本当は猫の耳がついているタイプのものにしたかったのだがそれはもう少し私がカワイくなってからの話だ。
あとはカバン。現在は、だいぶ昔に百貨店で購入した、黒のいわゆるビジネスバッグを使用していて、中にはパソコンケース、筆記用具、手帳、眠気覚まし兼口臭予防の板ガム、などが入っている。これら全てがカワイくない。まず黒の手提げ型ビジネスバッグを持っているハイティーンなんか見たことがない。いるわけがない。勤労に縁がないからだ。
「何も入るわけがないこぶし大のバッグ」を肩から提げている女性をよく見かけるのは、「道具」を携帯しないことが美しいとされ、わずらわしいものはパートナーの異性に持たせればよい、との考え方から来ているのだろうか。邪推自体が野暮であるのは承知しているのだが、あのこぶし大のバッグにはいったい何が入っているのか。
・カロリーメイト(栄養補給)
・小さめの水筒(水分補給)
・宝石(きれいだから)
・十徳ナイフ(護身、コルクの開栓など)
・折り畳みの晴雨兼用傘(急に雨が降ってきた際、あるいは紫外線避けに便利だから)
・ドアストッパー(引っ越しの時にあると便利だから)
・発煙筒(後方車両に危険を知らせるため)
・ブルボン 味ごのみ(おつまみ、行楽用)
あたりが予想されるが……。いや、スマートフォンか。あと財布。ともあれ、必要最小限のものを持ち運ぶという思想自体わたしも共感できるところである。ビジネスバッグではなく、パステル・パープル色の小ぶりなリュックサックを背負い、パステル・パープル色のカバーを嵌めたスマートフォン、パステル・パープル色の折り畳み財布のみを携帯することにした。妻子にバレると不信がられるので、駅前のコインロッカーで荷物を入れ替える。リュックサックには「クロミちゃん」「名探偵コナン:安室透」の缶バッヂをつけた。完璧である。日常からカワイくいるための闘いはとっくに始まっている。
—
「当店をどちらでご存じになりましたか?」
「インターネットの検索で。最寄りで通えそうな場所だったので」
予約の10分前に到着した私は、施術担当の女性とやり取りを交わした。料金の説明、必要時間、通う頻度の相談など。ある程度下調べをしたつもりであったが、実際に来店すると新しい知識が増える。周囲の客・店員も全員が女性である。20代から私と同じぐらいまで、年代の幅は広い。まずは簡単なアンケートを終えた。
「それでは、まずは手指の消毒からしていきます」
女性は霧吹きでコットンにアルコールを染み込ませ、私の手のひらと甲を丁寧に拭いた。それからやすりで楕円形に爪を整え、先端の細い電動カッターで甘皮処理というやつをする。私の40数年分の甘皮が削り取られた。
「では、ベースジェルを塗っていきます」
あまり頻繁には通えなさそうである旨を告げていたので、日持ちするタイプを選んでいただいたとのことだった。まず、第一層をこさえてその上からコーティングする形で美しい爪ができあがる、そんな当たり前すらも私は知らずに生きてきた。ベースジェルを塗られただけでもツヤが違う。強いLEDライトに照らされた自らの爪を、私はしげしげと見つめた。
「カラーとデザインはどうなさいますか?」
私はわかったような顔をしながら、提示された候補を眺めた。
「うーん。このなんか、きらびやかな……。ものをば、えー、お願いできれば」
「カラーは?」
「はい。パステル・パープルで」
「かしこまりました。それでは右手の人差し指から塗っていきますね」
右手の人差し指の爪の先にパステル・パープルのマニキュアが塗られていく。ひんやりとした感触と感慨を覚える。ますますカワイくなっちゃうではないか、と。
「ストーンはどうなさいますか?」
「ストーン?」
「あの、こういうキレイな石をつけたりもできるんですよ」
「ああ……。じゃあ、お願いします」
私はまるで味玉でもトッピングするかのようなノリで「パール」を追加注文し、それも右手の人差し指に乗せた。
仕上げ作業ののち、施術は無事に終了した。
「本当にありがとうございました。やる前は不安もあったのですが、カワイくしていただき、誠に助かります」
「いえいえ、男性のお客様はめずらしいので、わたしもすごくやり甲斐がありましたし、楽しかったです」
「そう仰っていただけますと、この店を選んで良かったなあと思えます」
私はパステル・パープルに照らされた私の指をもう一度見つめ、エレベーターに乗り、店を後にした。感じたことのない”万能感”に包まれていた。
エレベーターのドアが閉まると同時に、サロン内では「どしたん!?笑」「”カワイくしていただき、誠に助かります”笑」「やばすぎ、仕事どうするつもりなんだろ笑」などの爆発炎上騒ぎが巻き起こっていたことを私は知る由もない。
—
月日は過ぎた。
いよいよパステル・パープルに身を包む日がやってきた。妻子が外出している今しかチャンスはない。人目のつかない近所を少し歩く程度であるが、私にとっては大冒険だ。だいたい2人で買い物に出かける際は、ああだ、こうだと散々悩んでくるから帰宅は夜遅くになる。
全身を剃毛したうえ、パステル・パープルの肌着を着用し、パステル・パープルのワンピースに身体を通した。次に、パステル・パープルのロングヘア・ウィッグを軽やかに装着した。この薄い布一枚を隔てただけの私が春を駆け抜けるのだ。フリルのついたパステル・パープルの靴下と、エナメル素材のヒールを履く。もちろんパステル・パープルだ。それらは全て、不可侵である私の部屋のクローゼットに隠してあった。
蝶だ!蜂だ!春風に舞ったことがあるか?君たちは。私はその予定である。
……と、その時、玄関のドアががちゃり、と開いた。娘であった。
「ただいま。ママ、春物のコート選ぶんだって。時間かかりそうだからわたしだけ先に帰ってきちゃっ……」
娘は、絶句していた。紙袋をばさっ、と落とした。
「違うんだ」
何が違うというのか。
「……。」
笑うでもなく、叫ぶでもなく、母親に似たその目元はピクリとも動かなかった。
「私は父さんだ」
知っている。わざわざ言わなくてもいい。
「なに……やってんの?」
「あの……。春だ。春をやっているんだ」
「はる?」
「そう、春をやりに外で舞おうとしたその瞬間、お前が現れたというわけだ」
「頭おかしくなった?忙しいの?てかネイルやった?」
けっこう前からだよ。妻子とも、私の指先なんか注目する気すらなかったようだ。悲しいが。
「お父さん、お父さんにそんな癖(へき)があるんなら、言ってくれればよかったのに」
「言えるわけないだろうが」
「だってお父さん、普段何もしゃべらないじゃない。自分のこととか職場のこととか」
「興味ないだろう」
「ないけど」
「ほら」
「ただ、そんな爆弾抱えてるんなら、家族の問題だから。相談ぐらいしてくれても」
「爆弾だなんて失礼だな。春だって言ってるだろ」
「その春っていうの、一旦やめて」
「すまない」
「うん。でも、なんていうんだろう。気持ち悪いよ。気持ち悪いんだけど、がんばったんだね」
「そう……なんだよ。がんばったんだ。がんばったんだここまで」
全身パステル・パープルの40代成人男性の頬を、脂まじりの涙が伝った。ただ、私はカワイくなりたかっただけなんだ。
沈黙のあと、娘が口を開いた。
「あの、さ。今度出かけた時にさ。コスメとか見てみたりする?わたしとママと」
……。
「そうしていただければ、誠に助かります」
【告知】
2022/11/20 「文学フリマ東京35」に出展します。
(イベント詳細は公式サイトをご参照ください)
タイトル:『まったくドルフィンキックしたもの』
サークル名:目元付近
ブース:第一展示場/M-27、28
執筆者:城戸/sudo/virus菌/JET
価格: 800円
2019年以来の出展です。表紙は漫画家の風見2先生に描いていただきました。
何卒よろしくお願い申し上げます。本当に何卒よろしくお願い申し上げます。


 JET
JET




 城戸
城戸
 金輪財 雑魚
金輪財 雑魚
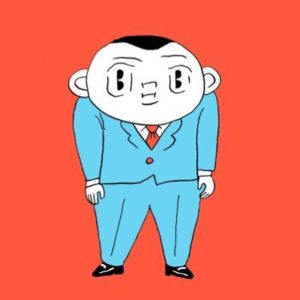 サレンダー橋本
サレンダー橋本









