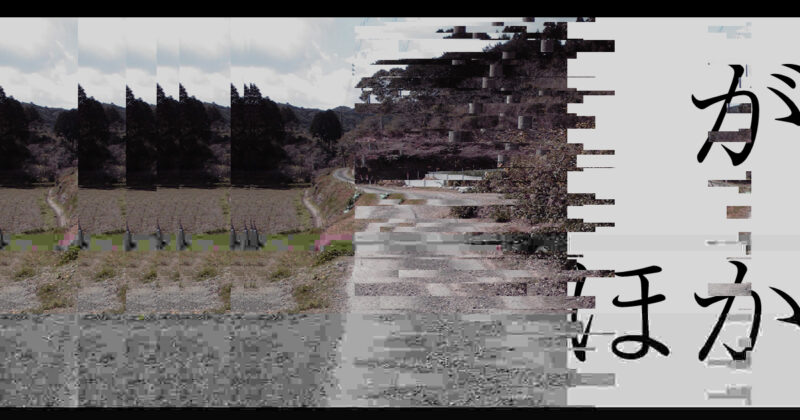今日は市が主催する合唱コンクールの日です。
お友達のプテラノドンくんが出場するときいたわたしは応援にきちゃいました。
「えっと控室はこのあたり・・・あっ!いたいた!おーい、プテラノドンくーん!」

「おや、たしか同じクラスの・・・」
「今日のコンクール出るんだよね。わたし応援してるから、がんばってね」
「ええまあ別に、誰の応援があろうとなかろうとやるべきことをするだけですがね」
まあ。せっかくクラスメイトから応援してもらっているというのに、なんてクールなんでしょう。普段からクール&ミステリアスな彼ですがここまでくるとちょっと薄情という気もします。
ですがよく見ると昼食中といった様子です。もしかすると食事の邪魔をしてしまったのかもしれません。

「よお、ここで会ったが百年目だな!」

「あっ」
あの人は、このあたりで最も実力があるといわれている合唱団の一員の方です。
彼とプテラノドンくんはこれまでに幾度となく同じ大会に出場しては、プテラノドンくんがいつも一位で彼が惜しくも二位という、いわばライバル同士の関係です。
「今日はいつもの中華まんじゃないんだな。そんなんじゃあ本番でフルパワーが出せないぜ?」
そう言われたプテラノドンくんはまるで聞こえなかったかのように無反応ですが、ライバルの人もそんなのはわかりきっていたという風に話を続けます。

「実を言うと俺は優勝なんてどうでもいいんだ。俺はただ終生のライバルであるお前に勝つために今日まで血のにじむような努力を重ねてきた。だから今日はお互いに全力でぶつかり合おうぜ!」
なんて情熱的な人なんでしょう。プテラノドンくんとはまるで真逆のタイプです。熱血漢というのはきっとこのような人のことをいうのでしょう。
あっ!こっ、これは!

ライバルの人が熱すぎて持ってきていた食パンがトーストになっています!
それだけ熱い人ということですね。

「別に誰が相手だろうと僕はやるべきことをやるだけですよ」
それにひきかえ彼はなんてクールなんでしょう。あんなに熱烈な宣戦布告をうけながら、表情にちっとも変化がありません。ライバルの人とは本当に真逆ですね。

クールすぎてトーストも元の食パンに戻っています。
「まあいい。お前との勝負、楽しみにしているぜ」
そう言うとライバルの人はどこかへ行ってしまいました。
今日のコンクールもまたプテラノドンくんが優勝することになるのでしょうか。それとも今日こそはライバルの人が勝つのでしょうか。
この勝負、いったいどっちが勝つのか目が離せません。
*

あれから事態は急変しました。なぜ、こんなことになったのでしょうか。
あの後、予定通りにコンクールは始まりました。
わたしも観客席で聴いていましたが、どの合唱団も本当に素晴らしい歌声でした。拍手のしすぎで手がいたくなってしまったほどです。
その中でもとくにすごかったのはあのライバルの人です。

最初に驚いたのは彼の合唱団の人数です。合唱団といいながらなんとステージにあがったメンバーは彼一人しかいなかったのです。
これは後で知ったのですが、彼の合唱団はたしかに彼を含めて20人以上はいるのですが、彼以外のメンバー全員が常にヒトの目ではとらえられない速さでステージ上を高速移動し続けているのだそうです。
なんでそんなことをしているのかと思いましたが、それにもちゃんとした理由がありました。
ライバルの人の歌声はこれまでに聴いたことが無いくらい伸びやかで力強いものでした。そこへさらに、他のメンバーが高速移動をすることによって発生させている特殊な気流が歌声の増幅装置として機能し、歌の質をさらに高めているのだといいます。

FIRE
EMBLEM~♪
歌であそこまで圧倒されるのは人生で初めての経験でした。
しかもその次はプテラノドンくんの番でしたから、あんな人とライバル関係にある彼の歌がどれだけすごいのか、最初に来たときよりもさらに期待は増していました。
それなのに。
プテラノドンくんはステージに現れなかったのです。

帰り道、すっかり日も落ちた寒空の下では小鳥のさえずりさえもきこえてきません。
結局、コンクールはライバルの人が優勝しました。

ですが壇上にあがる彼の顔はどこか不満げでした。それはやはり、「終生のライバル」とまで讃えた相手が何も言わずいなくなったからなのでしょう。勝負から逃げたとすら思っているのかもしれません。
どうしてプテラノドンくんは会場に現れなかったのでしょうか。理由は本人にしかわかりません。
疑問をかかえたまま帰路につきましたが、少し寄り道をすることにしました。
コンビニでなにか温かい飲み物でも買って、すっかり冷たくなった指先を慰めようと考えたのです。
「一緒に温かい食べ物も買おうかな。そういえばプテラノドンくんもお昼に中華まんを食べてたっけ。―――あれ?」
記憶の中でなにかがひっかかるのを感じた、そのときです。
「あっ」

「プテラノドンくん!?」
視界に飛び込んできたのは疑問を残したままいなくなった張本人でした。
ここは会場から少し離れた公園です。まさかこんなところにいるなんて。
「いったいどうしたの?なんでこんなところにいるの?」
呼びかけに気づいた彼は、いかにも弱った声でなにかを伝えようとしました。
「・・・さ・・」
「―――さ?」
「サマンサタバサ・・・」
「―――――サマンサタバサ――――?」
そう言い残すと彼は意識を失いました。
「サマンサタバサって、いったいどういうこと?」
理由も不明なままコンクールから失踪した彼が、公園のベンチにいたかと思えば今度は謎の言葉を言い残したまま意識を失ってしまいました。
”サマンサタバサ”。
意識を失う直前というタイミングでわざわざ言い残すからには、なにか意味があったはずです。
ですがそれだけではなにを伝えようとしていたのかわかりません。今日のこれまでの彼の行動や言動に何かヒントはなかったでしょうか。
「そういえば・・・」
記憶を逆行していくと、その中でいくつかの違和感があることに気がつきました。
そしてそれら点と点を線で結んだとき、ある一つの答えにたどり着いたのです。
「そうか!わかった!」
*

「おまたせ!プテラノドンくん、買ってきたよ!」
「あ・・・ありがとうございます・・・」





「やっぱりピザまんはうまいですね」
そう、彼は「サマンサタバサ」と言っていたのではありません。
彼は、「ピザまん食べたい」と言っていたのです。
おそらく弱っていたせいでうまく発音することができなかったのでしょう。
わたしが彼の発言の真意に気づいたのは、今日の彼の様子や周囲とのやりとりの中にいくつか違和感があったからです。
最初にそれを感じたのは今日のお昼にライバルの人が現れたときのことです。
ライバルの人はプテラノドンくんを一瞥するなりこう言いました。

「今日はいつもの中華まんじゃないんだな」
そのことを思い出してわたしは不自然に思いました。
あのときプテラノドンくんが持っていたのはたしかに誰がどう見ても中華まんでしたが、それだけでどうして「いつもの中華まん」ではないとわかったのでしょうか。

あのとき、プテラノドンくんの手にあったのは新品の中華まんで、まだ口をつけていませんでした。真っ白なその見た目だけでは中の具が何かなんてわかるはずがないのです。
それなのに彼がそう言い切れたのは、きっとプテラノドンくんがいつも食べているという中華まんが、中身を確認せずともぱっと見ただけでその見分けがつくものだったからなのでしょう。
肉まんやあんまんのように皮が白くない中華まん。そう、つまりいつもの中華まんとは、ピザまんのことを指していたのです。
そして違和感はもう一つありました。
それは飲み物のボトルが空だったことです。

わたしが彼に会ったとき、そばにあったペットボトルはすでに空でした。にもかかわらず手元の中華まんは一口も食べた痕跡がありませんでした。
多くの場合、食事をしていてまず始めにペットボトルの中身を全て飲み干す、という人はいないのではないでしょうか。事実、いまも彼は最初に手に取ったお茶をスルーしてまず口に運んだのはピザまんの方でした。
ここまで気づいた時点でようやく彼がここで動けなくなっていた理由も推測できました。
きっと彼はおなかがすいていたのです。
これは憶測ですが、彼が中華まんを食べなかったのはきっと、”合唱の前にはピザまんを食べる”という彼独自のルーティンがあったからなのではないでしょうか。
ライバルの人の発言からも、彼がこれまでもコンクールがある度にピザまんを食べていたということがわかります。
スポーツ選手や楽器演奏者など、一流のパフォーマーほどルーティンを大事にするとききますが、きっとそれはどの分野においてもいえることなのでしょう。
ピザまん以外の中華まんを食べてしまうとルーティンが崩れてしまう。そう考えた彼は目の前の中華まんを食べるということはせず、飲み物だけでお腹を満たそうとしたのではないでしょうか。
「―――――これがわたしの予想なんだけど、合ってたかな」

「すごいな、全てその通りですよ」
「あのあと結局おなかがすいたのでやっぱりピザまんを買いに行こうと会場を出ました。ですがあまりの空腹に、途中のこの公園で力尽きてしまったのです」
力尽きるくらいならピザまんじゃなくてもいいから食べれば良かったのでは。わたしがそう言おうとすると、まるでそう言われるのをわかっていたかのように彼は遮って言いました。
「ライバルとの勝負、全力で臨まなくては相手に失礼ですからね」
生半可な覚悟で臨むくらいならいっそ何も食べない方がいいと考えたのだと、彼はそう付け加えました。
それだけルーティン、もといライバルとの勝負に真剣ということのようです。それよりもいま初めて、彼自身の口からライバルという言葉が出ました。冷徹かと思いきや意外と熱い部分も持ち合わせているようです。

「よし、ピザまんを食べることもできましたし、ライバルとの決着をつけに行きましょうか」
「えっ、でもプテラノドンくん、もうコンクールはとっくに終わったよ?」
コンクールが終わってすでに時間もたってます。会場には誰もいないでしょう。プテラノドンくんの合唱団のメンバーはもとい、ライバルの人ももう家に帰っているでしょう。それでどうやって決着をつけるというのでしょうか。

「時を戻します」
「えっ!?プテラノドンくん、時を戻せるの!!?」
時を戻すということは、コンクールが始まる前にタイムスリップして、勝負をやり直すということなのでしょう。
でも果たしてそんなことができるのでしょうか。
「あなたも見たでしょう。トーストが食パンの戻るのを」
あっ!


たしかに見ました。あのときたしかにトーストはただの食パンに戻っていました。
「じゃ、じゃああれはまさか」

「僕がトーストの時間を戻しました」
す、すごい。そんなことができるなんて。普通の人間には絶対に不可能ですが、そこはまあ彼はプテラノドンなので、プテラノドンならそんな芸当ができてもさほど不思議ではありません。
「あのときトーストに最後の力を使ったせいでしばらく時を戻すことができない状態でしたが、空腹でなくなったいまならそれも可能です」
「あと、合唱団のメンバーのことなら心配ありません。僕の合唱団は僕一人ですから」
「えっ!そんなことがあり得るの!?まさかプテラノドンくんのところも他の人は高速移動してるとか!?」
「そんな高速移動がどうとか気流がどうとかいう屁理屈じみた不思議パワーを僕は使いませんよ。もっとロジカルな理由です」
「タイムスリップをすると当然その時間にいる僕自身とはちあわせるわけですが、同じ時間に同じ人間は存在できません。なのでその二人の意識は統合されるのですが、その際に記憶のほかに身体能力なんかも統合、つまり足し算されるのです。そうしてパワーアップした人間のことを、果たして一人の人間と、そう呼べるでしょうか」
「ということは、時を戻すたびに過去の自分自身と融合してパワーアップしていて、実質一人以上のマンパワーを有しているから”団”として成立しているってこと!?」

「その通り」
たしかにそれならメンバーが一人だけでも合唱団といってもいいのかもしれません。
どうやら合唱というものはわたしの想像以上に奥が深いようです。コンクールの運営陣はいったいどんな懐の広さで彼らのエントリーを受け付けているのでしょうか。
ともかく、ピザまんを食べたいま、プテラノドンくんは万全な状態です。これから過去に戻ることで本当の勝負を行うことができます。
「プテラノドンくん、がんばってね」
彼は無言で首肯すると、ゆっくりと両腕を広げました。

「GO OVER TIME & SPACE」




*

どの合唱団も本当に素晴らしい歌声でした。拍手のしすぎで手がいたくなってしまったほどです。
とくにライバルの人はすごかったです。世の中にあんな合唱のかたちがあるなんて。
さあ、次はプテラノドンくんの番です。あんな人とライバル関係にある彼の歌がどれだけすごいのか、最初に来たときよりもさらに期待は増しています。
あっ始まります。




こ、この歌声は!!

FIRE
EMBLEM
~~~~~♪♪♪
な、
なんてしなやかかつエネルギーに満ちた歌声!それに一人だけでこの声量はいったい!?まるで100人、いや、1000人以上で歌っているかのようです!
あまりにも優美にして荘厳!この歌をなんと形容すればいいでしょうか、大地に根付く大木の鼓動、心奪われる幻想的なオーロラ、神秘的な満天の星空、そのどれをも思わせ、そしてどれにもない圧倒的にして絶対的な世界観!!
「こんなにすごい歌があるなんて・・・!」
彼の歌に聞き入るあまり、曲が終わってもしばらくの間はその場にいた誰もが拍手はおろか、ささいな物音すら発することができませんでした。
ふと我にかえったときには時計の針は大きく進んでいて、それはまるでタイムスリップでもしたかのような感覚でした。
*

「負けたよ。だが次こそは俺が勝つからな。また会うのを楽しみにしているぜ」
そう言ったライバルの人の表情は悔しそうで、でもどこか晴れ晴れとしていました。
一方、優勝した本人はとくに喜ぶ様子もなく、いつも通りのクールな態度です。

「優勝おめでとう、プテラノドンくん」
「ありがとうございます。でも今回優勝できたのはあなたのおかげですよ」
「?」
プテラノドンくんはそう言ってくれましたが、わたしは自分がなにかしたという自覚はありません。
むしろ感謝するのはあんな歌を聴かせてくれたこちらの方です。
「そうだ、優勝のお祝いになにかごちそうするよ。といってもコンビニだけど」
プテラノドンくんは少し考えた後、

「では・・・、サマンサタバサ」
「え?サマンサタバサ?そんなのコンビニに売ってないよ?」
なんの冗談かと困惑するわたしを見て彼は短く、はは、と笑いました。いったいなにがおかしかったのでしょうか。
ミステリアスで謎の多い彼ですがこれ以上謎を増やされてはそれに悩まされるこちらの身がもちません。
サマンサタバサといわれても、困るんです。


 ありふれた平凡なドラマティック
ありふれた平凡なドラマティック




 雨穴
雨穴
 オモコロ編集部
オモコロ編集部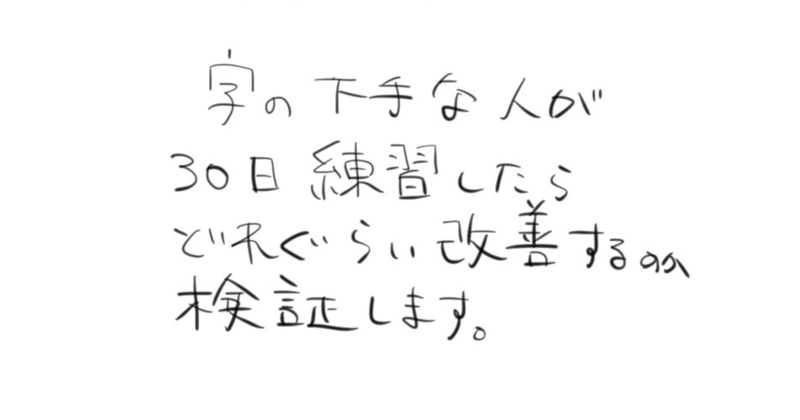
 藤原 仁
藤原 仁
 オケモト
オケモト
 たかや
たかや
 金輪財 雑魚
金輪財 雑魚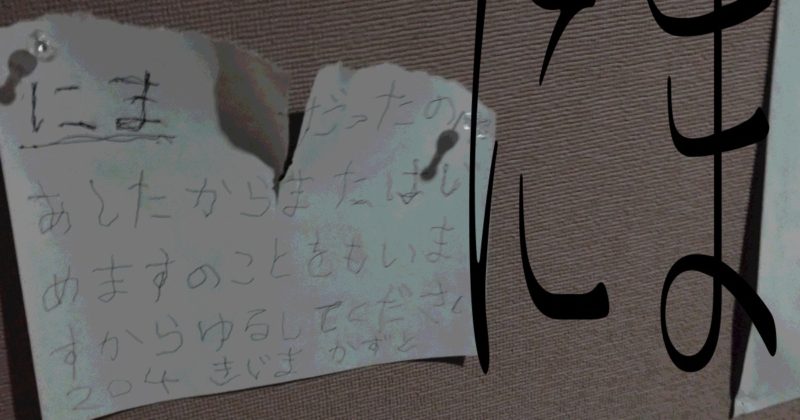
 梨
梨
 BIGSUN
BIGSUN 凸ノ
凸ノ