「はじめまして。待ちましたか?」
「いいえ、わたしもさっきついたばかりです。今日は寒いですね」
「ええ、本当に。ちょっとどこかに入って話しませんか?外だと凍えちゃうんで」
「はい、そうしましょう」
家の最寄駅から西武池袋線で四十分ほど揺られ、わたしは池袋駅にやってきました。年末のくそ忙しく、こんなくそ寒いたまの休日には家に閉じこもっていたいに決まっているのですが、今日しか都合がつかないとぬかしやがるのではるばる馳せ参じたのです。池袋という指定ですが、わたしの「埼玉県在住」との情報から気を利かせたつもりなのかもしれませんが、逆にこちらとしては子どもの頃から池袋なんか飽きて死ぬほど通い詰めてもう新鮮な気分になる余地なんか残されていないうえに、安居酒屋・オタロード・風俗街と、いい大人の出逢いの場としてはもっとも不適切であるといえます。この時点で期待薄で、悪天候もありわたしのテンションは低空飛行まっしぐらです。
現れた男性は、プロフィール写真より丸顔で、身長170センチとありましたが、目測165、6センチがせいぜいでしょうか。底が厚めのスニーカーでカサ増しをしているようですが、逆にせせこましい根性を表してしまっています。が、わたしとてプロフィール写真を”ささやかに”粉飾しているわけですからおあいこでしょう。
服装も、なんか妙にテカテカした、安物そうなダウンにジーパンです。あえて飾らない演出を施しているのかもしれませんが、飾ってください。多少は。水道メーター検針のバイトで食い繋いでいる売れないお笑い芸人じゃないんですから。余裕感の醸し出し方が裏目に出ているのか、単純に異性として舐められているのか、判断に迷うところです。
東口交番近くのカフェチェーン店に案内されました。このカフェチェーン店は、今時珍しく喫煙席が設けられています。わたしは、何を隠そうヘビースモーカーです。
「タバコ、喫います?」
「はい、いつもは喫うんですけど。今日は遠慮しておきます」
「え、いいですよ?喫っても」
「そうですか、じゃあお言葉に甘えて」
お言葉に甘えさせてもらうことにしました。何を隠そうわたしは毎日3箱以上は確実に喫うヘビースモーカーなのです。仕事でうまくいかない時はその倍は喫います。もう喫煙者には生き辛い世の中になって久しいですし、イメージの悪さは重々承知していますから、アプリのプロフィール欄では隠しています。職場の喫煙所に行くと、ほとんどがわたしよりも年上の男性スタッフばかりで、ここぞとばかりにわたしから「日常のちょっとした不満」を聞き出そうとしてきますが、わたしはのんびりと、孤独に、誰にも邪魔されずタバコをやりたいのであって、一切のコミュニケーションを断絶しています。
嫌な女に映っているでしょうがもう気にも留めていません。感情を殺し、表面上の愛想を取り繕うだけの「嘘」こそわたしは人生でつきたくないのです。だからわたしは「いいですよ?喫っても」の問いかけに対して躊躇せずに「お言葉に甘える」選択を取ります。「ありがとうございます!バカバカ喫わせてください!」と答えたいのを堪えているぐらいです。タバコとブラックコーヒーの組み合わせ、最高!
「介護の仕事をされているんでしたっけ。大変じゃないですか?」
「そうなんです。土日休みじゃないので、なかなか予定合わなくてすみません」
「いえ全然!こちらこそ貴重な週末なのに、すみません」
ほんとだよ。
「いつも休みの日って何をされてるんですか?」
警察密着24時の録画を観ながら、9パーセントの缶チューハイを飲むことです。人が警察の前で下手な嘘や言い訳をついている姿が心の底から好きなのです。
「わたしは……。そうですね。最近はサブスクで映画観たり、ドラマ観たり」
「へえ、最近ハマってるものとかあります?」
「海外のゾンビものなんですけど、次の展開が気になっちゃって、つい夜更かししちゃうんです」
これも嘘ではありませんが、まだ会話の展開があるかな?と思いジャブを打ちました。
「ゾンビものとか観るんですね、やり取りしてた印象と違うから驚きました」
なんじゃそりゃ。どう思ってたんだよ。
「そうですか?引きました?」
「いや、全然そんなことないんですけど」
「映画やドラマって、何をご覧になります?」
「あまり観ないんですが、強いて言うなら邦画のコメディが多いですね」
一番しょうもないやつだろ。漫画の実写化ばっかりしやがって。小気味良いテンポで進めばなんでもおもしろがると思ったら大間違いだから。あと、きれいな顔のアイドルに下品な言動させるのもいい加減にしてほしい。「意外性」が面白いと思っているのでしょうが、「意外性」が面白いと思う時点で裏切りでもなんでもなくて、逆方向に曲がって壁に激突し「面白いでしょ?」みたいな顔をするのはやめてください。誰にでも思いつきますから。だいいち、普段から日本人にまみれて散々働かされているのに、映画でまで日本人が喋っているところを見せられなければならないんでしょうか。我慢できません。
「邦画ですか。わたしはそこまで詳しくないので、今度おすすめ教えてくださいね」
教えてもらわなくても結構です。わたしが認めている邦画のコメディは寅さんだけです。
「ぜひ!よかったら今度映画でも観に行きましょう」
……それから、他愛もない話をして解散しました。東京は夕方からますます冷え込み、これからまた埼玉まで四十分かけて帰るのかと憂鬱になりました。拒否するのも気の毒なので、ラインの連絡先だけ交換しました。帰りの電車で、「今日は楽しかったです、寒い中ありがとうございました」「いえいえ、また機会があれば是非!」と空疎なやり取りが続きました。機会があれば。機会、か……。郊外へ戻る車窓から外の景色を眺めながら、明日から始まる仕事のことを思い出し、せめて休日の間ぐらいは忘れていたかったのになあとため息をつきました。
—
年末、二十二年ぶりの完全新作で『男はつらいよ おかえり寅さん』が公開され、わたしは心から楽しみに劇場へ向かいました。2時間弱の上映が終わり、わたしは「うーん。これじゃないなあ」と作品の出来栄えに不満を覚えていました。シニア世代が当時を懐かしむ同窓会の題材として使われているだけのような。
もやもやした気持ちを抱きながら、映画館から出ようと乗ったエレベーターの中で、先日マッチングアプリでお茶をしたあの男と出くわしました。なぜ。
「わっ、奇遇ですね!もしかして寅さんですか?」
さもわたしが寅さんそのものであるかのような声のかけられ方に恥ずかしさを覚えました。
「ええ、そうです。こちらこそびっくりしました。寅さんがお好きなんですか?」
「はい、実はシリーズ全部観てるんです。いやー、面白かったなあ」
面白かったんかい。「共通の趣味を持つ」人と「価値観が相入れない」苦痛はえも言われぬものがあります。
「どうでした?」
「はい、わたしも面白かったです」
思ってもいないことを言ってしまいました。いつからわたしは思ってもいないことを言うのに躊躇しなくなったのでしょうか。タバコを喫わせてほしい。
「この後って暇ですか?」
暇です。が、断るのに適当な言い訳が思いつきません。時刻は18時過ぎ、夕ご飯に丁度いい時間ですし、おそらく食事の誘いでもする気でしょう。帰り道にスーパーで惣菜を買い、家で強い酒を煽りながら人が警察にしょっぴかれるところを観てもいいのですが、少しくらいなら暇つぶしにこの男に付き合ってもいいかなという気になりました。いっぱいお酒飲んで奢ってもらおう。
「いえ、特に予定はないですよ」
「じゃあ、いっしょにご飯でもどうですか?」
「ええ、いいですよ」
また池袋で捕まっているのがわたしの非常にダサいところです。
—
もらった。この出逢いはもらった。あとはインサイドキックで軽く合わせるだけだ。
まさか寅さんが出逢いのきっかけを作ってくれるなんて。ありがとう寅次郎。結局、出逢いなんてものは運命次第であるから、あれこれ打算で取り繕ったとしても無意味なのだ。マッチングアプリで繰り広げていた右往左往が伏線となり、巡り巡ってチャンスとなって降り注いできた。OK,Google、近隣のイタリアンないしはフレンチの店を教えたまえ。女性は全員イタリアンないしはフレンチが好きと相場が決まっているのであるから。俺は1件目にヒットした、池袋西口のワインビストロを目指した。
—
デザートのティラミスを食べ終えると、彼女はお手洗いに立った。俺はのんきにスマートフォンをいじりながら、このあとはどこか近場のバーにでも誘うか、その後は……。などとよからぬ妄想を膨らませていた。5分ほど経ったが、彼女はまだ戻らない。化粧直しもあるし、女性のお手洗いは時間がかかるものだから……。と悠長に待っていたが、10分経過してもまだ戻らない。具合でも悪いのだろうか?心配していると、ふとひとつの疑問が頭をよぎった。
もしや、お会計を済ませるための間(ま)なのではないか?しかしながら、彼女は1杯800円ほどのグラスワインを6杯は飲んでおり、ドリンク代だけでいえば俺の倍以上費やしている。ここで気を利かせてお会計を済ませたとして、果たして俺は後から彼女にお代を請求できるだろうか?みみっちさが過ぎるのはわかっているが、だとしても、人の倍飲んでおきながら、たとえ一時的にとしても全額を相手に負担させるのはどうなのだろう?そういうもの?しまった。つべこべ考えていないで、さっさと会計を済ませて席で待っているべきだった。完全に機を逸した。このタイミングで会計を済ませている背中を晒すほうが逆に気を遣わせてスマートではないのではないか?この駆け引き何?俺が勝手に駆け引かれてると勘違いしているだけ?発生してないよね?駆け引き?ていうか、帰ってくるの遅くない?助けに行ったほうがいい?
と、そんなくだらないことで悩んでいるような人間が周りに1人もいないような場所でエアーで七転八倒しているうちに彼女が戻ってきた。別段、体調の悪そうな様子もなく、食事中と同じく、ほんの少し口角を上げてうっすらと笑みををたたえている。
「じゃあ、行きましょうか」
「そうですね。とりあえずお会計を」
俺は財布を取り出した。
彼女はほんの少し口角を上げてうっすらと笑みをたたえている。
のみだった。
—
「支払いは?」
「と、いいますと」
「いや、開き直られても」
「開き直ったつもりはありませんが」
「正直、どう思いました?あなたがトイレから戻ってきたタイミングで、俺が会計を済ませていなかった時に」
「正直ですか?払ってないのかよと思いました」
戦いの火蓋が切って落とされた。ような気がした。お互いにとって。
「え?はなから人の金で飲む気満々でワインをばかばか飲みくさっていたのですか?」
「そうですよ。だってあなた、面白くないもの。お金ぐらい支払っていただいてもよいのではないですか?」
「ちょっと待ってくださいよ。寅さんの話であんなに盛り上がったじゃないですか」
「いや、寅さんは人情や温かみがどうこうじゃなくて、寅さんがいかにクズで社会不適合者かを観て笑うものですから」
「そんな性格の悪い見方をしていたんですか?そりゃあ人の金で酒ばかばか飲むはずですよ」
「あなた年収いくらですか?身なりといい、年収400万円本当にありますか?400万円あったら、女性と食事して1万円弱支払うのにここまで揉めるとかないですよ。ぱっと支払って2軒目でも誘いますよ。どうせやることやりたい気分だったんですよね?でもわたしは、あなたに奢ってもらって、あとはダッシュで逃げようと考えていました。本音をいうとね」
声のボリュームが上がる。店内がざわつき出す。
「他のお客様のご迷惑になりますから、よそでお願いします……。」
店員が退店をうながしてきた。できるだけ2人を刺激しないように。
「もういいです。わたしが支払いますから。カードでお願いします」
—
「渾身の力を込めてあなたをぶちのめしたいという熱き情熱が湧いて参りましたので、いまから公園にでも行きませんか」
「のぞむところです。よろしくお願いします」
2人はコンビニエンスストアで缶ビールを購入すると、西池袋の劇場裏の公園に移動した。
「あなた、本当の年齢はおいくつですか?」
「30です。巳年です」
彼女はいけしゃあしゃあと答えた。
「あなた、マッチングアプリでは20代後半で登録してましたよね?首筋とか手の甲を眺めていて、とても同年代とは思えませんでしたよ。」
「最低。あなただって年収サバ読んでますよね?」
「いや、それはまだはっきりしてないじゃないですか」
「どうなんですか?」
「サバ読んでいました」
女は仁王立ちだ。男がどう見ても劣勢である。
男はやっと切り返した。
「そ、それだったら歳上になるじゃないですか。最初から奢ってくれればいいのに」
「最初から奢ってくれればいいのに?情けない。食事に誘ってきたのはそっちじゃないですか。誘ったほうがお代を払うのがマナーではないですか?しかも結局わたしが支払いを済ませているんですが。口座教えるんで半額振り込んでもらっていいですか?」
「半額?あなたあれだけ1杯800円もするワイン飲んでおいて?」
「別にいいですよ。このまま私が支払いを済ませても。二度と会わないだけですし。では、さようなら」
「さようならじゃなくて、一言謝ってほしいだけなんです」
「何に対してですか?支払いも済ませました。年齢詐称も明らかになりました。何に対しての謝罪ですか?早く帰りたいんですが。警察密着24時の録画を観たいのですが」
「ぐぬぬ」
「”ぐぬぬ”とはっきり口に出しておっしゃいましたね。お疲れ様でした。それではさようなら」
女が闇に消えていく。背中が徐々に遠のいていく。ゲームオーバーである。
スコアが画面右上に表示される。コンティニューのカウントダウンが始まった。
—
「本当に勝てるようにできてるの?何回挑んでも君が闇夜に消えていくんだけど」
「君が下手くそなだけだよ。最初にプロフィール設定があるだろ?もっと数字を盛ればだいぶ楽になるよ。どうせゲームなんだから遠慮するなって」
「そうは言うけど、無課金だから限界あるって、ステータスの上限的に。君ってこのアプリ、いくらぐらいお金かけてるの?」
「うーん。少なくとも、今回のワイン代ぐらいは遣ってるんじゃない?」
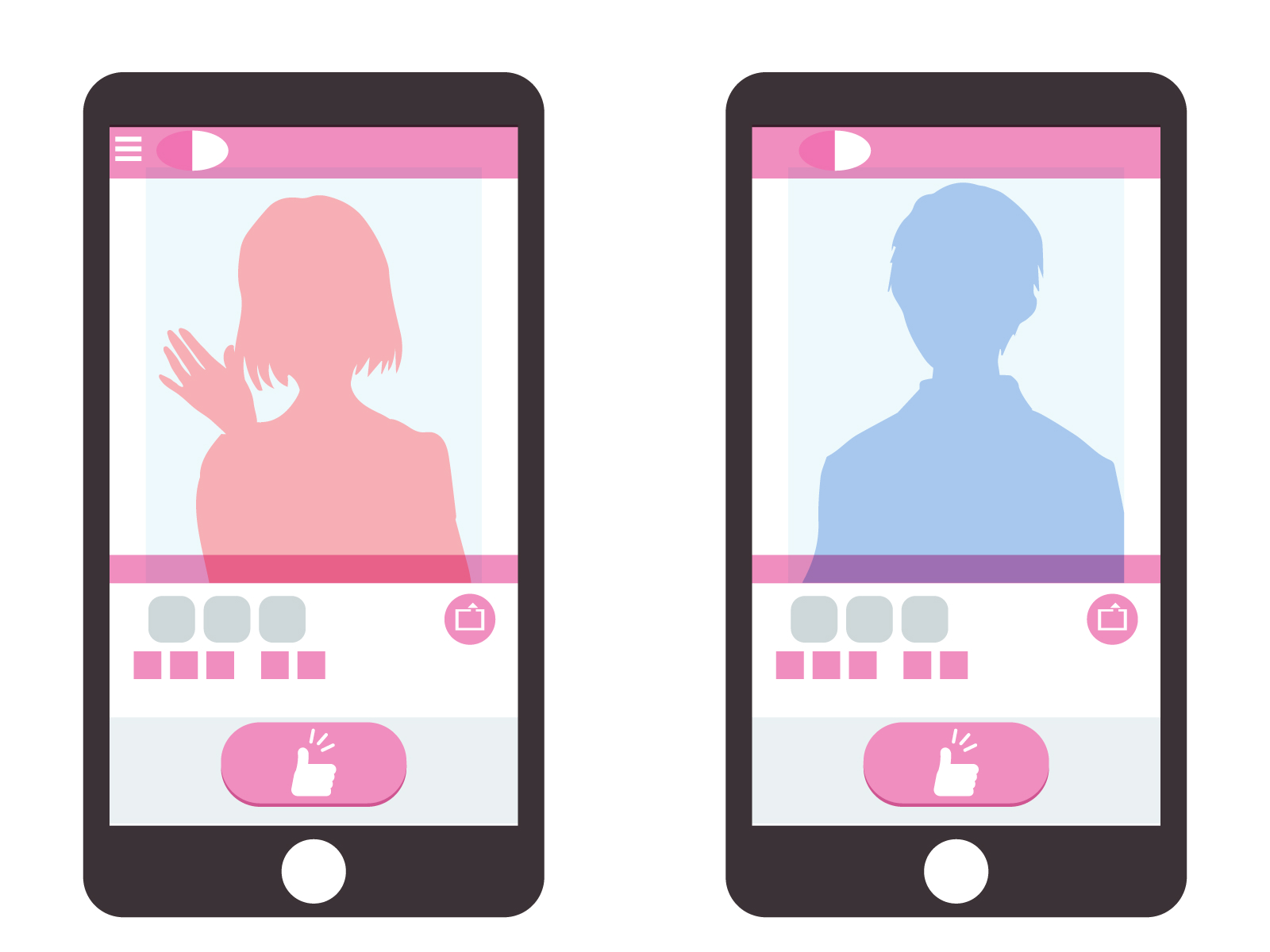

 JET
JET




 ダ・ヴィンチ・恐山
ダ・ヴィンチ・恐山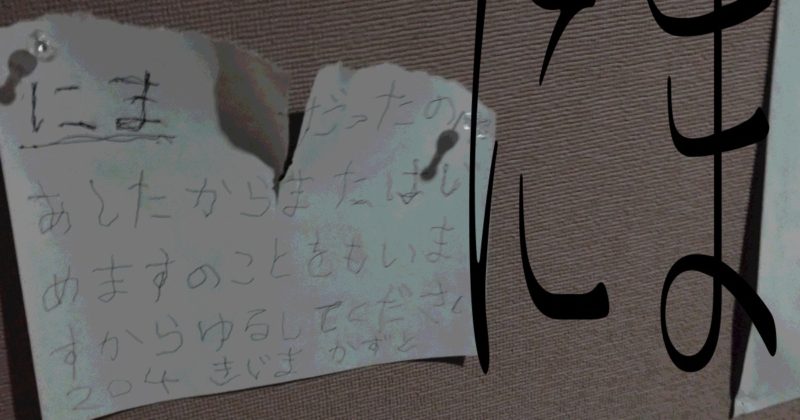
 梨
梨
 雨穴
雨穴
 城戸
城戸
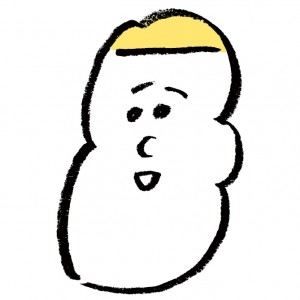 小山健
小山健







