上京する前、俺の秘密を唯一打ち明けた友人がいた。
青木のかっちゃんである。
青木のかっちゃんは、高2の修学旅行日に集合場所に現れず、みんなを散々待たせた挙句に会場に現れず、そのまま高校をフェードアウトしていった男である。背が低く色白で無口の目立たないやつだった。誰かとつるんでいる様子もなかったが、いじめられているなんて話も聞かずその失踪は学年を揺るがせた。が、旅行の日に相当のヘイトを買った以外は誰の印象にも残らず、皆は卒業し、無責任にもそれぞれの道を歩んだ。
俺が学校に来なくなった青木のかっちゃんにたまたま出くわしたのは、地元のイオンモールのさびれたゲームセンター、というか、プレイコーナーだった。夏休みに素っ裸で高校野球を観ていたのだが、「こんなはずではない」との正体不明の焦燥感にいてもたってもいられなくなり、財布とスマートフォンだけを持って自転車で走っていたところイオンモールの駐輪場に辿り着いていたのであった。
しょうがない、時間でも潰すか、と隣接するイオンシネマの上映作品を調べたが、特に興味のある映画がなく、なんで甲子園ですら観たくないのにアオハラないといけないんだよ、しかも千円を支払って。おかしいぜ。とか、特撮の劇場版なんて観てられるかよ、おたくじゃあないんだから。とか、さんざん心中で悪態をついた挙句、適当に時間を潰せそうなメダルゲームを探すことにしたのである。
プレイコーナーに入ると、自分と同じようにただ時間をベットし、「MOLLY FANTASY」と印字された0円相当のメダルを稼ぐ服装に色味の少ない連中が集まっていた。しめしめ。俺は空虚を愛する男だ。と、両替を済ませ、いったいなにがどうなれば正解なのかわからない虹色の塔にメダルを投入。すると、ゲームが終了した。
あっけに取られ、しばらく口を半開きにしながら塔の天井を見つめた。高校野球の中継で聴いていた「紅」のブラスバンド演奏が頭で流れた。気を取り直し、今度はスロットマシンならばいけるだろう。数字を揃えればいいから。特に7を。と場所を移そうと歩き出したところに、どこかで観たような顔の男がこちらに向かってくるのに気がついた。
「あ」
ほとんど口を利いたこともなかったが、背の低く色白の、まさに青木のかっちゃんだった。まだ打ち解けていなかったから、その時は以上でも以下でもない「青木」だった。引き返そうにも正面同士で、今から舵を切るのも間に合わなかった。
「青木くん?」
「お……火野くん。久しぶり。夏休み?」
「うん、まあ」
気まずい空気が漂った。
「そっちは夏休み?」
「うん。暇つぶしに」
「そうか。じゃ」
青木くんはそそくさと立ち去った。どことなく、スロットマシン、なんかやってる場合でもなくて、そんなら今ならどうしようかな、と思った。青木くんの背中を目で追っていると、ある筐体に座り、ポケットから取り出したカードホルダーを外した。
よく見るとそれは「ぷよぷよ」だった。「ぷよぷよ」て。子どものころ、誰かの家でやったことがあるような、ないようなで、隅っこにひたすらぷよぷよを積み上げ、まぐれで連鎖が繋がればラッキー。と、盛り上がらない対戦を数十分続けて、やめた。あの「ぷよぷよ」じゃないか。あんなにつまらないゲームやってるんだ。学校辞めてまで。と、己のことも棚にあげて彼を腐した。
対戦が始まったみたいだ。次に何色が落ちてくるか、まるで予知できているかのように規則正しくぷよぷよを積み上げていく。天井すれすれだ。欲しかった赤色が落ちてきた。連鎖だ。1、2、3、4、5、え?6、7、8、9、10、11、12、13、14、15。止まった。相手を透明のぷよぷよで窒息させ、完膚なきまでに潰した。「ぷよぷよ」ではなく「暴力」だった。
連勝は止まらない。破壊的に強い。悪夢のように降り注ぐ透明のぷよぷよ。俺は夢中で彼のゲーム画面を見守っていた。画面で連鎖に火がつくたびに、心の中で「1、2、3……。」とカウントした。
ぷよぷよの下に何人もの屍を沈め、青木くんは席を立った。
「ねえ、今の半端ないね」
思わず声をかけてしまった。
「見てたんだ。別に大したことないよ。あんなの」
「いやいや、まったく誰も相手にしてなかったじゃん。オンラインでしょあれ?すごすぎない?」
「でも、何にもならないしさ。学校こないでずっとやってたら、誰でもあれくらいにはなれるんじゃない」
「そんなことないと思うけど。圧倒的だったよ。あまりにも」
俺はいつになく興奮していた。青木くんの表情は涼しげだが、少しだけ嬉しそうにも思えた。
「じゃ、帰るわ。あんま学校で言わないでね」
「あ、青木くん」
「何?」
「俺もとっておきに意味のない技を君に披露したい」
「は?」
俺は半ば無理やりに青木くんをプレイコーナーから連れ出し、イオンを出て、二人、河川敷まで自転車を漕いだ。やぶ蚊の飛び交う橋桁の下へ向う。ひどく蒸し暑い。汗だくである。周囲に誰もいないことを確認した。
「見ててよ」
俺は掌から火の玉を繰り出し、川に投げてみせた。
「な?意味ないだろ?」
青木のかっちゃんとは以降、俺が地元を出るまで、しょっちゅう遊ぶ仲となった。のちに聞いたところによると、青木のかっちゃんはこの時、完全に殺されると覚悟していたらしい。
—
とうとう、就職活動もうまくいかず、いったん地元に戻ることにした。大学は一応出られたから、実家暮らしをしながら近くの企業を探す。久しぶりの実家である。一人の自由気ままな生活でないから、ワム!のウキウキ・ウェイク・ミー・アップを躍りながら歌ったり、笑ったり、人々に愛と勇気を与えることもできなくなってしまった。最悪である。余生である。
うーむ。ひさびさに自転車で、近所のイオンモールになんぞ足を運んでみるかあ。凱旋だ。なんていったって俺は東京の大学を出ているのだ。ひれ伏すがよい皆の衆。って、うそうそ。でも、仲良くしてくれたら嬉しいぜ。と部屋を出ようとすると、祖父が訪ねてきた。と同時に、胸ぐらを掴まれた。祖父に。俺、成人してしばらく経つのに。
「死ね」
死ねと言われた。
「さもなくば」
胸ぐらを掴んでいる右手が灼けはじめた。
「継げ」
紫の閃光が炸裂した。体は吹き飛び、壁に叩きつけられ、布団の上にどすん、と落ちた。
何が起こったか理解ができない。頭脳が真っ白である。
後頭部を踏みつけられた。
「東京でだらだら過ごしてどの面下げて家に帰ってきたんだ。何を学んだ。何を身につけた。誰と出会った。糧になるものが、一つでもあったか。炎の才能にあれほど恵まれていたのに。さんざん自由に過ごしてこのザマか。大馬鹿者。この手で貴様を燃やし尽くす。しかし、継げば許す。炎忍(えんにん)の正当継承者として名を連ねる腹を括るのであれば、貴様を許してやる。どうする。灰になるか、名を継ぐか」
後頭部がだんだん熱くなってきた。祖父に踏まれながら焼かれるのか。新聞になんて載るんだろう。孫殺し、だけでも大騒ぎなのに、踏まれ焼かれた場合。「踏焼死」。聞いたことがない。三流のパンクバンドか。
「どうする。さあ、どうする。答えろ」
くそ。この炎で食えりゃそりゃいいよ。でも、じいちゃん。あんただってそろばん塾の先生だろうが。炎で食ってるわけじゃないだろうが。継いでどうするんだよ。どうなるんだよ。父ちゃんが諦めちゃったし、俺まで諦めたらもうとうとう最後だろうってこと?勝手すぎるだろうが、知ったことじゃないよ。自由にやらせてくれよ。血とか、伝統とか、いいよ。どうでも。ここで、はい。って言えばいいの?じゃあ、継いだってことになるわけ?それでいいの?俺が結婚して、子どもが生まれたとして、その子の人生まで決めるのか?権利がどこにあるんだ?自由主義バンザイ。俺で終わらせてやる。ていうか、人の頭踏んじゃダメだろ。爺ちゃんだとしても。爺ちゃんだからこそ。うん、就職できなかったのは申し訳ないけれど。だからって殺されるってバランスがおかしいだろ。ふざけるな、ふざけるな、ふざけるな、ふざけるな。
全身の血液が泡立った。紅蓮の火炎竜巻が垂直に巻き起こった。木造建築の中で。
—
『阿多古祀符 火迺要慎』と書かれた、愛宕(あたご)神社由来の火の用心のお札がある。愛宕神社とはホノカグツチを祀る神社の総称で、総本山は京都にある。京都は木造建築の多い街並みであるから、火事を極端に恐れる。特に料理屋などでは、厨房にこのお札が貼られ、「火にまつわる災いが起きませんように」と祈る風習が今もなお残っている。火野家の神棚に貼られたお札は、最上に神力の込められたものだ。つまり、家の中で爆発・燃焼が起こっても一切燃え広がらない・燃え移らないほどの、効力を持っているのである。
—
紅蓮の火炎竜巻が垂直に巻き起こり、傾斜したり回転したりした。とっさに祖父・龍斎は身を翻し、急な階段をすべるように駆け下りた。とても80歳が近いとは思えない身のこなしである。階段の下で振り向くと、紫に輝く炎を両手に灯らせた。迎撃の構えである。炎太は、足裏から炎を放ったまま宙に浮き、ぐぐぐ、と体をくの字に曲げるやいな、ぴん、とまっすぐ一気にエネルギーを放出、さながらミサイルのように、待ち構える龍斎をぶん殴るべく、斜め下へと一直線に吹き飛んだ。轟音がした。母親は居間での韓国ドラマの視聴をやめ、駆けつけた。父親は役場で、クラフトボスを飲みながらテンキーを打っていた。
—
一ヶ月半が過ぎた。
祖父の傷は致命傷には至らなかった。あらゆる火炎や爆発が家庭内で収まり、祖父と孫の殺し合いは世に情報が出ることがなく済んだ。のほほんと鼻水の滲んだ秋だった。祖父は著しく喋るスピードが衰え、物覚えが悪くなった。父親と母親とで、もしかしたら、どこかホームに預けたほうがいいのではないだろうか、と具体的な話が進み出した。
斜め下方向への敵意を持ったミサイル突撃を悔いた。足の裏に血流を集中させたことを悔いた。俺自身が生き残る為にああするしかなかったとはいえ、もっと遡れば、ちゃんと努力をしていればよかったのである。一から算数ドリルを解いていれば、こんなことにはならなかったのである。
祖父の老人ホーム代はせめて捻出する責任がある。とにかく職に就こうと動き、駅前のビジネスホテルのフロントバイトを始めた。夜勤で割もよく、平日は特にヒマで一人の時間が多い。二人交代制で、ペアで入った社員と入れ替わりで休憩している最中、シーフードヌードルをすすりながら、スマートフォンにイヤホンを挿してYoutubeを眺めていると、おすすめに一本の動画が表示された。
『奇跡の15連鎖』
再生すると、コントローラーを握りしめた襟が蛍光色のシャツを着た小柄の男が、ぷよぷよで大逆転勝利を収めていた。客席は大歓声で沸いている。
間違いない。
青木のかっちゃんだ。
シーフードヌードルをすする手はすっかり止まっていた。青木のかっちゃんは感慨深げな表情を滲ませている。司会者らしき男がマイクを片手に青木のかっちゃんに近寄った。
「見事、優勝の座に輝き、賞金100万円を手にした青木選手に盛大な拍手を!」
「ありがとうございます。誰からも省みられずに単純に続けてこられただけなんですが、ただただ嬉しいです」
青木のかっちゃん、ぷよぷよで食ってるじゃん。
俺は涙が止まらなくなった。
青木のかっちゃん、爺ちゃん。俺決めた。炎の忍者で食っていくことにする。明日バイトやめよう。
炎の忍者でやっていく。どうやるかは具体的には定まって・いない・ウェイク・ミー・アップだった。


 JET
JET


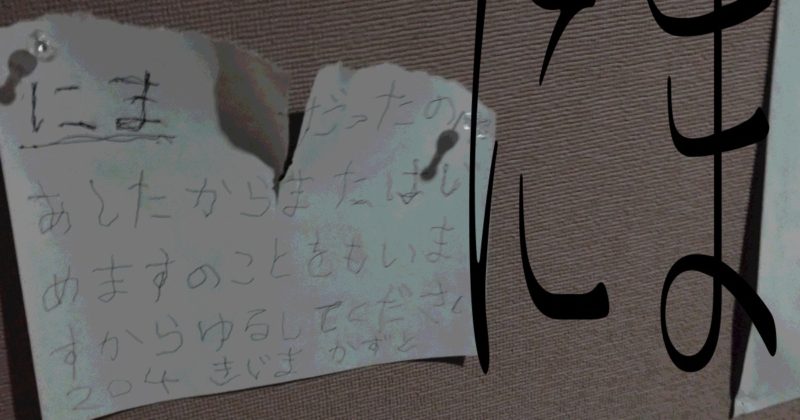
 梨
梨
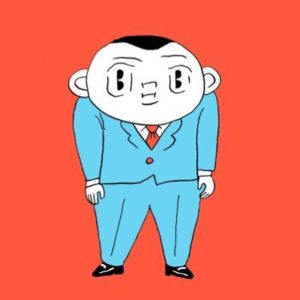 サレンダー橋本
サレンダー橋本
 金輪財 雑魚
金輪財 雑魚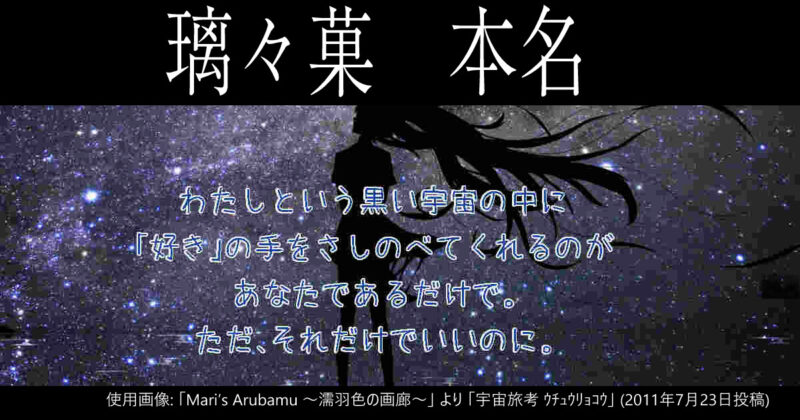

 エマゴー
エマゴー







