言った側は覚えていなくても、言われた側は覚えている。そんな経験が、言った側、言われた側、いずれにしても、あなたにもあるのではないでしょうか。
例えば、「行けたら行くわ」という文言は、履行されない約束の代表格として扱われていますね。言われた側も「行けたら行くわ、か。どうせ来ないだろう」とタカを括りますし、言った側も「行けたら行こうという言葉を発した時点では”行けたら行く”つもりであったのは事実で、よしんば誘いに行けなかった場合は、なんらかの不都合な要因が発生したからだ」と弁明できますから、実に日本人的な、行間を読むことを強いる、便利なフレーズだと思います。
「行けたら行くわ」の中に「どうせ来ないんだろ」「どうせ行かないよ」の不文律が含まれているとしたならば、じゃあ、「本当に行った」場合は果たして「迷惑」なのでしょうか。
「なあなあ、来年の1月に温泉旅行に行かない?」
「うーん、行けたら行くわ」
「了解。まあ、じゃあ都合ついたら連絡して」
〜1月〜
「お待たせ。宿、じゃらんで見たけど綺麗そうだったね。ご飯も美味しそうだったし。楽しみだな〜」
「本当に、来るんかい」
と、このようにいきなり待ち合わせ場所に現れるのは極端なケースですが、「行けたら行く」と留保するのであれば、最初から「行きます」と言ってくれたほうがよい。と、いう言い分と、「行けたんだから行ったんだよ」という言い分がアンビバレントに存在する状態。は、できるなら避けたい、面倒だから、と考えるのは私だけでしょうか。ややこしいですか。
—
大阪府大阪市住吉区、南海電車住吉大社駅から東に徒歩5分、阪堺電車住吉鳥居駅前から徒歩30秒のところに、大阪市南部では随一の由緒正しき神社である「住吉大社」がある。住吉鳥居駅前には、「もっちもち、もっちもちだよ、もっちもち」「お餅好きにはたまらない」と延々声を張り上げる男性が軒先に立っているお餅屋があって、いったん彼を無視したり、一瞬横目に見て、やっぱり無視したり、境内の屋台で唐揚げ買って食べたいから、お餅は遠慮しとくわ、と体よく断ったり、押しに負けて蓬餅を買ってみて、「外で食べると、案外おいしいね」と話のネタにしたりする。初詣の季節はとてもよく賑わって、毎年200万人が訪れる。関西圏にお住まいで、人混みが嫌いでなく、初詣ぐらいはしとこか、ほどの、ほんの少しの信仰心がおありならば、初詣に出かけたことのある方もおられるかもしれない。
住吉大社は「子宝祈願」の神社である。室町時代のころ、いまで言うところの粉浜商店街の惣菜屋のあたりで暮らしていた、じいさんとばあさんがいた。仲睦まじくはあったけれども、残念ながら子宝に恵まれなかった。さすがにもう子供でもこさえよか、という歳でもなくなってきた。しかし、余生を共に過ごすには、幾年月過ごせばよろしいんやろか、あんま考えんとこか、ぼーっとしてきたわ、お茶飲も。みたいにもなってきたのだが、でもなんかどことなく寂しい。そのへんを走っている子供を家に上げて、二十分ぐらい「最近何が流行ってんの」とか訊いてみるのも、子供らにしてみればたまったものではなかったのだが、じいさんとばあさんの限られた余生の端っこを埋めるぐらいの暇つぶしにはなった。
ある正月、じいさんがばあさんを住吉大社、こと「すみよっさん」に初詣でも行こや、と誘った。とはいっても、昔のじいさんばあさんというのは、昨今のじいさんばあさんとは比べようもないぐらい信仰心が篤くて、普段そんな神社とか興味ないけど、せっかくやし初詣ぐらいはいっといたろか、どうせやることなんかないし、暇やし。ぐらいの感覚ではなく、「さあ、正月や!今年もぎょうさん詣でまくったるで!まずは一発目、いってみよか!」と熱量を込めた、渾身の詣で、をやったりまっせと息巻いているのだった。
「すみよっさん」に近づくにつれ、普段とは見違えるほどの人の群れ、まったく、どいつもこいつも、他に行くとこはないんかいな、正月ぐらいじっとしてたらよろしやんか、と、白い息と文句をこぼしながらも、鳥居をくぐって、晩から夜明けにかけて降っていたみぞれを踏みしめつつ、びちゃびちゃの草履で並んで歩いた。
「ばあさん」
「なんですか」
「なんのお願いすんの?」
「なにをまた、ずけずけと。あんまし人に言うと、神さんも逃げていく気がするからやめて」
「勿体ぶりよって。どうせ腰だの膝だの痛いのを治してほしいです、とかそんなもんやろ」
「どうせ、とはまた、自分のお願い事がさも高尚かみたいに」
「そない正月から喧嘩腰にならんでもええやろ」
と、丁々発止というか、蛙鳴蝉噪というか、音と音のぶつかり合いみたいなやり取りをしながら、初詣を済ませた。
話は変わるが、神社で参拝するときのマナー、として、「二礼二拍手一礼」というものがあって、今では境内の、手水舎の横っちょのあたりに看板が立っていて、赤い生地に白の水玉のスカートを履いたツインテールの少女が神妙な面持ちでマナーを実践するイラストが貼られていたりする。あれを言い出したのは、少なくとも時代が平成に移ってからで、いつの間にかメディアの力によってマナーが世の中に浸透し、知ってないと大人として恥ずかしいよね、みたいな空気が醸成されていった、気がする。
また、これはお寺で適用される作法ではないから、お寺で賽銭を投げる時に「あれ、お寺さんやと二礼二拍手一礼、いるんやったっけ」となり、手に持ったスマートフォンでおずおずと調べてみて「ああ、お寺さんは参拝のマナーが違うんやわ、お寺さんはパンパン、てしたらあかんねやて、静かに一礼、それから合掌、でいいみたい」とお父さんとかお母さんに教えて、改まって静かに参拝を済ませる、みたいな、余計なシークエンスが挟まれてしまう。
神様、仏様の前でスマホをぽちぽち触っているほうがよっぽど無礼な行為なんじゃないかという気もしてくるから、二礼二拍手一礼みたいな後付けのマナーは取りやめにして、気ままに参って気ままに帰れるように奨励してほしい。それはともかく、じいさんばあさんは、ゼロ礼一拍一礼、と、いまの時代ならば後ろに並んでいる客から白い目で見られかねないオリジナルの作法で参拝を済ませたのだが、現代の人なんかよりよっぽど神様を深く真剣に信仰していた。
さて、今日やることは、これでおしまい。帰ろか。
室町時代は、まだテレビ朝日で『志村・所の戦うお正月』は放送されていなかった。志村けんも所ジョージも生まれていないし、テレビがないからだ。「正月特番」が「正月」に収録されていないのを知ったのはある程度大人になってから。志村も所も、たぶん10月半ばぐらいに赤と青の紋付袴を着て、「あけまして、おめでとうございます!」とやっているわけだ。ということは、「対決VTR」はもう少し前、下手すると8月終わりの、残暑のまだまだきつい頃に、中堅タレントや若手芸人たちがスタジオに集められて「あけまして、おめでとうございます!」と騒いでいるわけで、季節感もへったくれもない。志村も所も今ではお亡くなりになってしまったから、それらももうすでに過ぎ去った平成の風物詩である。
「じいさん、あれ、なんか聞こえへん?」
家の近くまでやってくると、ばあさんが、道端に転がっている布のかたまりを指差した。
「なんやろ。なんぞ気味の悪い。どっかのけとこか」
じいさんが手を伸ばそうとすると、それは赤ん坊であった。しかも、大きさは大体一寸程度、樫の木のどんぐりかと思ったが、手足が生えてるし、か細い声で泣いている。
「こりゃ赤ん坊やわ。えらい小さいなぁ。どうしてまたこんなところにこんな小さい赤ん坊がおるんやろうか。寒くて寒くて可哀想なやっちゃで」
「ああ、じいさん、私がさっき、すみよっさんで”子どもが欲しい”って手を合わせてしもうたからやわ」
「ええっ、またそれはえらいスピード感というか、怒涛の展開というか」
ばあさんの願いがすみよっさんに通じ、特急で受理されて叶ってしまった形だった。サイズ感だけ気にはなるが、じいさんとばあさんは、喜んでこの赤ん坊を育てることにした。今まで子宝に恵まれなかったものだから、手塩にかけられてかけられてかけまくられながら、彼はすくすくと育っていった。
—
十数年の月日が流れ、赤ん坊は立派な青年に成長した。
彼の持って生まれた長所は、じいさんとばあさんのお願い、依頼を、文句も言わずにすべて実行してくれるし、自分で「こう」と決めたことをやりぬく根性だった。手のかからないのは素晴らしかったけれども、あまりにもスキがなく、可愛げがなかった。そして唯一の欠点、欠点といっても彼がそう望んでこの世に生まれたわけではないから彼に非はないのだが、十数年経って、目鼻立ちもくっきりし、眉毛凛々しく、うっすらあばたもできて、喉仏も固く膨らんできたのにもかかわらず、体格は、道端で転がっていたころのまま、つまり、一寸から成長していないことだった。
手先の器用なばあさんが縫った、貴族風の、若草色の直衣を身に纏って、腰から米粒のような瓢箪をぶら下げている。彫が深いから、何を着ても様になる。上下オーバーサイズのセットアップを着用し、真ん中分けにしてオフホワイト×ナイキのエアマックスでも履けばそうとうモテたはずなのだが、まだそれらは存在していない時代だし、なんにせよ縮尺が一寸である。一寸だから食費もかからず済んで、じいさんばあさんにも負担なく育てられたというのがあるのだが。
一寸はある日、じいさんばあさんに「都会に出て行って、バリバリ稼いで、綺麗な奥さんがほしい」と言い出した。じいさんばあさんに孫の顔を見せてやりたいのもあるし、いつの時代の青年であっても、立志の心が芽生える、というのはごくごく自然な成り行きである。都まで出るのは、船で川を下っていくのが手っ取り早い。お椀のボートに、箸のパドルでええやんか、とじいさんが冗談半分で言ってみたら、それを鵜呑みにした一寸、箸を真ん中を削って持ちやすくし、両手で握ってパドルのように扱えるようにしてしまった。それでは行って参ります。だって行きたいから、と、意固地になって、心配するじいさんばあさんの声は届かない。が、当然である。80いくかいかないか、というじいさんばあさんの懇願なんかでは、たとえ一寸といえど10代の若者の「これから世に出てやんよ」という圧倒的推進力の前では完全に無力である。
お椀のボートと箸のパドルで、一寸は川を下って都会を目指した。頭の中は夢と希望で満ち満ちていて、じいさんばあさんの不安そうな顔なんか川を下り始めてから小一時間ぐらいで忘却の彼方にあった。
下流に行けば行くほど波も収まって、風も気持ちよくまさしく順風満帆であった。一寸は、とりあえず、もっとも豪華で立派で、柱の数が多くって、偉そうな人と綺麗な人が暮らしている屋敷の門を潜って、そこで働かせてほしい、と思った。川の水面の高さからでも、紅葉も終わり、焦げたキャラメルのような色になった生駒山がくっきりと映えて見えた。無言でケーブルカーに乗る、生駒山上遊園地までわざわざ来ているのに仲の冷え切った謎のカップルの距離感まで計り知れるぐらい、よく澄み渡った青空であった。
その生駒の山上遊園地にも匹敵するぐらい、優雅で堅牢で、冬の季節に好きな娘でも連れてきてぐるっと一周回り、その後夜ご飯を食べて家でネットフリックスでも見ようや、となるところまでイメージの湧くほどの屋敷が目に留まった。一寸は、ここなら俺の働くのに足る仕事場や。なにをやらせてくれるのかは知らへんけれどもどんな職場にだって困りごとのひとつやふたつぐらいあるやろ。体は一寸ぽっちしかないが、それ以外のハンディキャップは一切ない。俺より小回りの利く奴なんか都にだっておらん。絶対に俺ならここでうまくやってみせる。覚悟しとけや都会もんども、と門の前で仁王立ちをした。すると、タイミングよく向こう側から門が開いて、よくよく栄養の行き渡った長い緑髪の美しい姫君がこれまた勇ましく立っていた。
「鬼に嫁いでいけばええって?それって私の人権とかどうなってんの?」
「これ以上鬼が暴れ回ると民の暮らしもにっちもさっちも立ち行かなくなってしまいます。誠に申し訳のないことでございますが、鬼の言葉を鵜呑みにすれば、人々から巻き上げた金銀財宝で潤い、必ずや満足の行く暮らしを遅らせてやるから心配すんなや、短い人生、どうせ宮中で退屈に暮らすんなら、散々贅沢して笑って暮らそうや、笑える時代、作ろうや。とのことですので、ちょっとプライドとか、いったん捨てていただきまして、民と我々のためにも、鬼に嫁いでいただくわけにいきますまいか」
「まあ、鬼っていうたかって、ガタイもいいし、ケンカが強いのは当たり前に強いし、毛深くて半裸で角の生えてるのだけ我慢すれば、ちょっとごっついおっさんみたいなもんか。私は歳上全然ありやし、先に死んでくれたら遺産とか全部私に来るやろうから、しばらく我慢すればええか。うん。ええよ」
「ご快諾いただけたようで何よりです。それでは参りましょう」
従者に導かれて、姫君は街の方角へと歩いて行った。
「おい、姫」
「誰?誰か呼んだ?」
「ここや、足元よう見い」
「え?うわ、ちっちゃい男の子が喋ってる。ちっちゃくて顔かっこいい男の子が喋ってる」
「ちっちゃいは余計や。いまから鬼のとこに行くの?しかも嫁ぐって?そんな姿見たら、父上も母上も、街の民だって悲しむんと違うの?」
「私やってほんまはそうしたくないけど、なんか贅沢してくれるっていうし、そもそもお父さんもお母さんが、嫁いだってくれへんか、すまんの、と頭下げてるぐらいやし、民に何言われるか知らへんけど、しばらく黙ってたらみんな忘れるやろ。ていうか、そんなやいやい言うくらいなら、誰か鬼退治してやんねん、この俺が、私が、ぐらいのこと言ってくれる人が出てきたっていいやんね。みんな鬼にビビリくさっちゃって、命だけは勘弁してください、欲しいものがあったらなんでも獲ってってください、って泣いてるばかり。どうせ生きてたって何事もなく死んでいくだけなんだから、私の為にカッコよく散ってくれる人が現れたっていいのにね」
「ああ。それが俺よ。まかせとけ。鬼は俺が殺ってこます」
姫は、あまりにもストレートかつ予期せぬ台詞に面食らった。何度この子の顔を見ても、まなじりは切れ長で、こちらを見つめる瞳は、角度こそ下から見上げる形ではあるものの、吸い寄せられるような不思議な力があり、顎もシャープで首も長く、顔かっこいい。ただ、如何せん小さい。ちびである。ちびであるという言葉が合っているのかわからないほどのちびだ。よしんばこの子と喧嘩になったとして、踏みつけてしまえば私の勝ちだと思った。良心の呵責はあるにせよ、一寸ほどの、思い切り踏みつけてしまえるサイズの男が、一丈をゆうに超える鬼に勝てるとは思えない。
「うーん。気持ちはありがたく頂戴するんやけど、親もなんや嫁いでこい、言うてるし、都がボロボロに荒らされるんも困るし。あ、もし、鬼のこと、やっつけてくれたら、あなたの嫁にもらわれてやらんこともないよ。待ってるからね、なんて」
「言うたな」
「なに?」
「言うたな。待ってるって」
「なになにもう。怖いって。あんた顔かっこいいんやから。そんな顰めっ面せんと。ほなね。急いでるし」
まったく中途半端に「待ってるからね」なんて言ったものだから、言葉を額面通りにしか受け取れない一寸、その目はギラギラと茜色に燃えだした。
—
一年ほど経って、姫は鬼との暮らしにすっかり馴染んでいた。ひっくり返っていても運ばれてくる、鯛や鯉や鹿や雉や猪や餅や酒や柿や桃。都の屋敷でも散々美味しいものは食べてはいたが、やはり人目を気にして多少は遠慮していたものの、「さあ、どんどん食え」と鬼が言うので、よっしゃ、とばくばく食った。姫は若いから代謝も良く、庭は広くて運動できるスペースも存分にあったので、乗馬で腹直筋と腹斜筋をほどよく鍛えたり、暇つぶしに呼んだら現れるぼんくらの貴族どもと蹴鞠を楽しんで有酸素運動をしたりして、ぶくぶく肥えるようなことはなく、全然細くて、かわいいままだった。全然細くてかわいいから、カジュアルもフォーマルも赤も青も紫も緑も橙も金も銀も似合った。
鬼も「何を着てもかわいいなあお前は」と喜んで、都からありとあらゆる上等な絹をぶんどってきて、仕立てさせた。美味しいものを食べて、美しい洋服を着る。そして、私はかわいい。姫はほぼ、この暮らしに不満を持たなかった。不満があるとすれば、鬼がブスで下品でつまらないことだった。しかし体はでかいし、豪快でよく笑うので、根暗よりはましか、面白くはないけど、守ってはくれるし、と、その辺は妥協していた。
苦しむ民らからは恨みの声も上がっていたが、それを尻目に「誰も助けてくれへんからやん。私は悪くないもん」と開き直って贅沢三昧しているところに、鬼の従者の男が駆けつけて申し上げることには、身長がものの一寸足らずの男が、鬼を出せ、勝負しろ、必ず殺す、と門の前で騒いでいるとの知らせだった。
「おい、鬼。出てこい。一寸だ。必ずこの俺がしばく。殺す。殺して仕る」
「ええい。どこおんねんほんまけったくそ悪いボケほんまうっさいのおほんま」
「ここやここ。どこに目ぇつけとんねんお前は。足元や、くっさいお前の足元や」
一丈ほどもある赤鬼、声のするほうに視線を向けると、姿形は人間なれども、吹けば飛びそうな大きさの、童の玩具と見紛う男が自分に向かって声を荒げているのだった。
「あ?お前か、うっさいのは。なんぞピーピーと。ピー助か。お前は」
鬼は、しっかり面白くないことを言った。
「ピー助ではない。一寸だ。一寸だから一寸という。お前を殺しにきた。一年前に交わした、姫との約束を守る者だ」
「アホぬかせ。お前のようなピー助。なんやピー助って。おもろ。なんかあれみたいやな。あの、ほら、春先によく畑にいる。ほら」
鬼は、自分の発言に自分でツボった挙句、喉までたとえを出そうとして、結局出せなかった。一寸は、この男と暮らしている姫は、さぞや毎日辛い思いをしているに違いない、一刻も早く救わねばと闘志を燃やした。
「つべこべ意味もなく面白くもないことをぬかすな。さっさと武器を取れ。姫を返せ」
「あ?お前みたいなちびに武器なんぞ必要あるか。徒手で十分。秒で捻り潰したる」
鬼は、「秒で」とか、聞いたような言い回しを使った。鬼は喧嘩が強いから、その圧力で人が笑わざるを得ない、というだけの様子を見て、自分にはユーモアのセンスも備わっている、と勘違いしていた。だから「秒で」とか「霊長類最強の」とか、どこかの誰かが編み出した一昔前のフレーズを恥も外聞も年甲斐もなく使った。財宝や食糧や衣服だけでなく、ユーモアまでもぶん取って我が物顔。世が世なら、インスタントラーメンのテレビコマーシャルを制作していただろう。
「隙あり!」
一寸は、一気に間合いを詰め寄ると、鬼の喉元目掛け、剣を突き刺そうと飛び上がった。剣といっても、服を縫うのに使う針。屋敷で小間使いが落としたのを腰に下げていたのだった。
勝負あった。なんと鬼は、飛びかかってきた一寸を、そのままごくんと丸呑みにしてしまったのである。拍子抜けの結末だった。離れたところで様子を伺っていた姫は、けっ、なんか面白そうになってきたのに。おもんな。ピー助って。そっちもおもんないし。しょうがないか。こんな戦もなくて平和な時代に面白いことなんか言ったって意味ないしね。帰ろ。と、鬼に礼や労いを述べるでもなく、裏に引っ込もうとした。その刹那、鬼が悶絶する声が耳をつんざいた。聞いたこともない、野太い大音声であった。
「うぎゃああああああああああ。痛い痛い痛い。腹が痛すぎる。あれみたいや、ほら、水辺の蟷螂の腹の中から出てくる、ほら、あの、うぎゃああああ」
鬼の胃袋の内側で、一寸は剣を手当たり次第に、振り回し、突き刺しまくった。最期まで適切なたとえを出せないまま、胃袋をかっ捌かれて、粘膜を抉り取られ、臓腑を撒き散らしながら、出血多量で、鬼はあっけなく無惨に死んだ。ずたずたに切り裂かれた腹の壁から、真紅の鮮血に染まった一寸が這い出てきた。一寸は、もう死んでいる鬼の右の目玉を、もう絶対蘇ったらあかん、何も見るな、何か見たらしばく、見なくてもしばく、と、串刺しにした。姫はその姿を、あんぐりと口を開けながら見つめていた。
「あ、あんた、ほんまに来たの」
「ああ。あんたが待ってるって、言うたからな」
そんなこと言うたっけ。姫は、うかつに喋ると本気になる人もおるのか。まあ、それはおるか。私、めちゃくちゃ可愛いし。忘れてたわ。と今さら思った。一寸は、姫と別れてから一年の間、屋敷に勤め、主に害獣駆除を一手に引き受けて糊口をしのぎつつ、実戦の訓練を重ねていたのだった。
「あんた、それにしても、相変わらず小さいなあ。もし私より背が高くてカッコよかったら、付き合ってあげてもいいのに」
「ほんまか。しかしな、そればっかりは俺にどうすることもできん。山羊の乳を飲んだり、シラスの小骨を齧ったりしてはみたんやが」
足を引きずって、鬼の死骸を片付けている従者が「そういえば、なんでも願いを叶えてくれる小槌があって、でも、鬼の旦那が”別に全部叶ってるもんな、いらんわ、ほかしとこ”と蔵に置いておいてある小槌があった。あれ、ものの試しに使こてみたらどうやろ」と提案した。姫が、ほな持ってきて、と話半分で依頼、その黄金の小槌を握りしめながら「この男の身の丈よ、六尺にまで伸びろ」と一寸に頭めがけて振り下ろすと、一寸は、痛った、と叫んだ後で、みるみるうちに姫の身の丈を追い抜いて、手を繋いで歩いたら、丁度いい塩梅のサイズ感に成長した。
「うわ、かっこよ」
そうして、顔の可愛い女と顔のかっこいい男は、末長く幸せに暮らした。来年の初詣は、すみよっさんの近くの餅屋で蓬餅買って帰ろ。

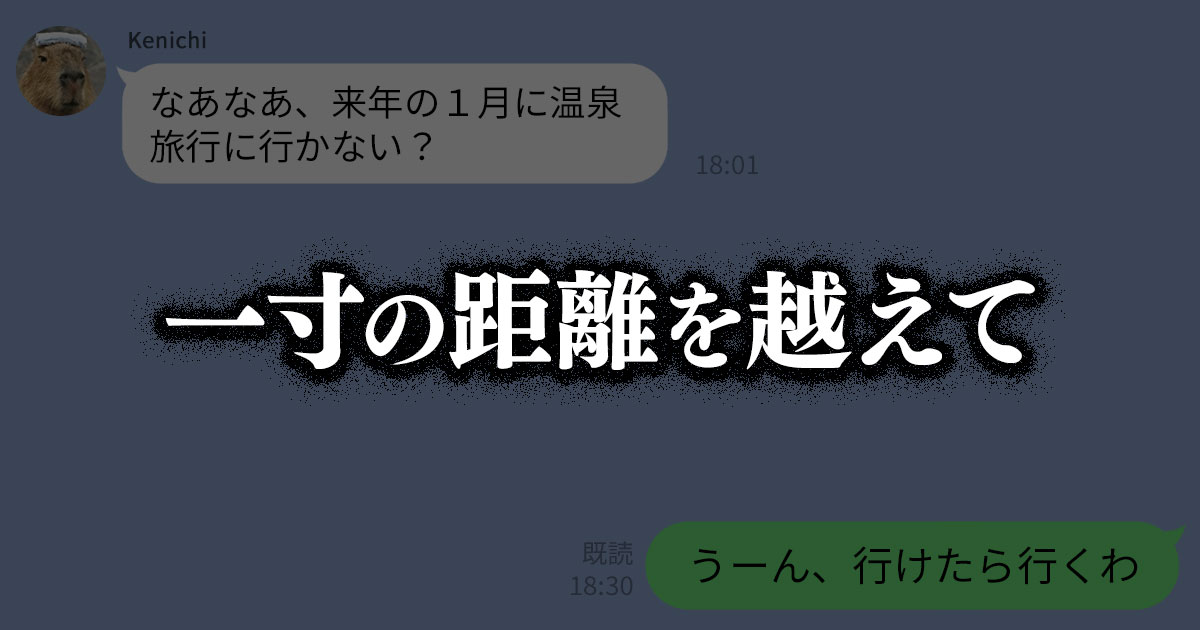
 JET
JET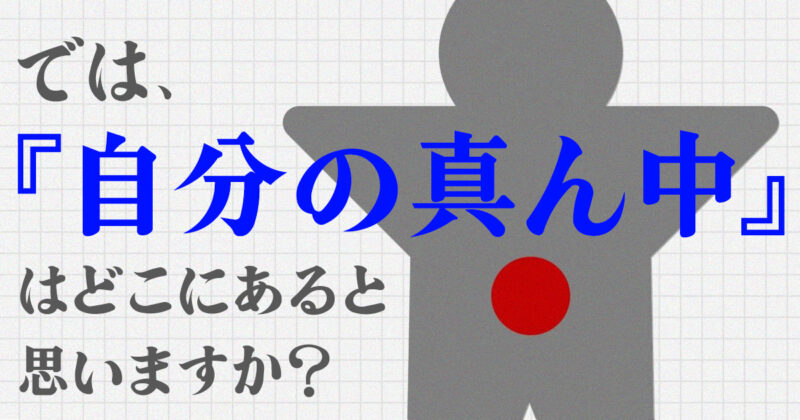
 ペンギン
ペンギン
 梨
梨
 彩雲
彩雲
 鳥角
鳥角
 サイケ蟹光線
サイケ蟹光線







