私はしょうがないジジイである。しょうがないジジイであり、しょうもないジジイである。もっといえば、しょうのないジジイでもあってる。私自身しょうのないジジイであることに薄々勘づいてはいたものの、そうはいっても、やはり自分がしょうのないジジイであると突きつけられるのはしんどい。なんていうか、お金もないし、地位も低いし、嫁はババアだし、嫁がババアなのは私がジジイだから致し方ないんだが、お金も地位もないんだから、せめて、ハートの部分は綺麗でありたい、と願っていた。
自分の性格のことなのに「願う」というのもおかしな話だが、なぜか自分の性格でさえも「他人事」のように感じてしまうのは、おそらく、私が今まで生きてジジイになるまで、本当の意味で「自分と向き合う」という行為から逃げてきたからに他なるまい。だから今回、斯様な「愚行」に出てしまったのも、自分の責任であると承知したい気持ちを持ちつつ、しかし一方で、「ほんとうに私が悪いのだっけ」と、呆けたような頭で、表情で、立ち尽くしたり、誰もいなくなった薄暗い四畳半を眺めたりしている。
ババアは泣いた。私は「ババアなんだからみっともない。泣くのはよしなさい」と思ったが、一緒に暮らすようになって、ここまで悲しみに明け暮れるババアの姿を見たことがなく、どういうふうに声をかけたらいいか、そしてどのように弁解したらよいか。私は途方に暮れるばかりだった。そこで私は、どの時点の、どの行動が間違いで、今回の結果を招いていたかを振り返り、もし同じような事態が今後発生した際に、二度と同じ過ちを繰り返してはならないと反省すること、そしてその姿勢をババアに見せることで信頼回復に努めるべきではないかと考えたのだった。
—
その日も、いつもと変わらない豪雪の朝に、私は薪(たきぎ)を担いで、街に商売に出かけた。この薪は、春から秋にかけて伐採したカラマツを、風通しがよく、雨に濡れない場所で乾燥させてある。米の取れない閑散期に準備しておいて、冬になったら街に売りに行く。
武家屋敷や城では炭を用いるようで、炭焼き場を所有している農家は木材を炭に加工して、それを売っているようだ。薪よりはだいぶ儲かるようだが、私は炭焼きの技術・設備を持ち合わせていないし、武家や城といったいわゆる権力者、もっといえば「太客」に繋がるパイプがないから、もっぱら庶民が買うための、安価で粗末で簡素な薪を売ることしかできないのである。
「薪を売る」行為は、その冬を越すための一時しのぎの稼ぎしか得られないから、このままであれば私は来年の冬にまた、松の木を伐採し、加工したうえで、街まで売りに出かけるだろう。しかしそうなれば「冬の間、街に繰り出す」ことが発端となった「愚行」が再度繰り返されてしまうかもしれない。それに、なるべくババアのそばにいてやる時間を増やして、ババアの心配を取り除き、ケアすることが、ババアの信頼回復に繋がる一端となるのではないか。
つまり「財産を増やす」「ババアのそばにいる」が解決のための方策となるわけだが、今日の明日ので炭焼きの技術や設備が手に入るわけではないし、私はジジイだから、残された時間もごくわずかだ。世帯所得を増やすためなら、ババアにも働いて貰えるに越したことはないのだが、ババアも足腰が弱くなってきて、暖かい季節に農作業の手伝いをしてくれるぐらいならまだなんとかなっているものの、いつまで持つかもわからないし、寒い冬の朝から陽の暮れるまで森林伐採なんて重労働をさせるわけにもいかない。だから「ババア、冬は体にこたえるから、家にいてくれ」と指示してはみるものの、何ら任せる仕事があるわけではないから、人材として塩漬け状態になってしまっている。そうして思案しているうちに、雪が融けて、緑が芽吹いて、コメが実り、また雪が積もって、そうしてやがて私もババアも死ぬ。ある意味幸せなことかもしれない。しかし、これは、飢饉や、自然災害や、戦乱が発生しなかった、自然と世間の歯車にうまい具合に組み込まれた時の話であって、サイクルのどこかでエラーが発生してしまえば、その時点で我々の生活は終わる。薄氷の上を恐る恐る踏み渡っていくような暮らしは「暮らし」とは呼べず「サバイバル」に近い。
こうして考えていること、それがすなわち行動と呼べるのだろうか?私の答えは否だ。考えと行動との間には、つねに大きな隔たりが存在する。ジジイである私が、ババアである妻を抱えて、世の中を生き抜き、最後は笑って死ねるようにするための行動を編み出した上で、なおかつ実行に移してこそ価値がある。
私がどうしてここまで余裕のある暮らしにこだわっているかというと「ハートの美しさ」なんて所詮「余裕」であるかないか、というだけの話であるに過ぎないからだ。清貧なんて言葉はまやかし、貧すれば鈍する。私の歩んできた狭い世界、狭い人生で得た数少ない真理だ。ここまで辿り着いている。75年ぐらいかかってしまったが。辿り着いているからこそ「では、どうすれば?」の壁を超える力のなさが歯痒く、それならば、何も気が付かないで朽ちていくほうが幸せであったかもしれないと考えてしまう。もう10年、いや、5年早ければ、と考えているうちにも時間は過ぎて、雪が融けて、緑が芽吹いて、コメが……。いや、もうよそう。曇天を舞う雁(がん)の群れの「アア、アア」という嘆息のような合唱がこだましている。
—
いったんこの堂々巡りと「そもそも論」に回帰する悪い癖をやめよう。単なる現実逃避だ。きちんと、シンプルに、私の「愚行」について目を向けなければならない。
その愚行とは「覗き」である。若く美しい女性を家に招き入れ、泊まらせ、禁止されていたにも関わらず、好奇心、いや、隠さずに言えば「性欲」に駆られた私は、女性の泊まる部屋の扉を開け、その姿態を目に焼き付けようとしたのだった。
私はその愚行に出た際、バレなければ罪ではない、と自分に言い聞かせていて、よしんばバレてしまったとして、「家に泊まるほうが悪い」「もっと言えば、豪雪の日に泊めてやった”恩”が私にはある」と、詭弁と呼ぶしかない言い訳だけを懐に忍ばせていた。
しかも、その女性を泊めていた数日の間、どういうわけか音に聞こえた「京友禅」とか「西陣織」といったような、都の絢爛豪華な反物があつらえてあって「ぜひ街で売ってきてください、いいお金になりますから」という。女性を泊める部屋には、もう長いこと使っていない機織り機があり、ギッタンバッコン音がしていたから「どうやら反物を織っているようだ」と気にしてはいたのだが、果たして素材になる糸をどこから調達しているのかはわからなかった。それはそれとして、おいおい本当かよ、いい値段で売れそうだなと薪の代わりに反物を担いで城下町に行くと、予想を遥かに上回る金額とペースで売れたのだった。私は調子に乗って、正月でさえ口にしたことのない大きな鯛と、酒を買ってきて、鍋にした。翌日も反物を売り、鍋。その翌日も鍋。冬の鍋ってサイコーだね。なあババア、なあお姉ちゃん、とか騒いで、酒を飲んで、笑った。
踏みとどまれるポイントを挙げるとするならばまず、ここだった。贅沢はしないで、ひと冬かふた冬は財産を蓄えておけば、炭焼き場の元手ぐらいになったかもしれない。
鍋もそろそろ飽きてきたから、次は工夫をして、雪の下で保存してあった菜っ葉と一緒に鯛をまるごと焼いてみよう。と思った。それを女性に相談したところ「アクアパッツァ」みたいでいいですね、と言った。余談だが、この地方には「赤八(あかはち)」という郷土料理が現代に至るまで伝わっている。水産資源の乏しい山間部ではあるが、主に正月の贅沢として「鯛の丸焼き」を振る舞うようになったのが起源と言われており、「赤八」をつつきながら美味しい酒を飲んでお屠蘇気分になっている成人男性のことを「あかぱっつぁん」と呼ぶ。ババアは「私は鍋でいいよ」と言ったのだが「つまんねえな」とその意見を却下した。
食事が終わって、また女性が「それでは、これからわたしは反物を織りますので、再三申し上げておりますけれども、作業中は絶対に戸を開けないでください。何卒よろしくお願い申し上げます」とうやうやしく三つ指を突き、丁寧にお辞儀をして四畳半に引っ込んだ。
私とババアが寝支度に入ってからも、ギッタン、バッコンは続いていた。ババアが寝息を立て始めたぐらいのタイミングで、私は、連日、ひさびさに栄養のある食事をしたこと、慣れない酒を飲んだこと、が重なって、薄紅色の煙が頭の中に充満くるような気がしたのだった。美麗な反物という貴重な物品の授受と、大雪の間の宿泊施設ならびに食事の提供、を天秤にかけて、あちらサイドは衣食住の「衣」こちらサイドは「食住」と1対2だから、こっちのほうに恩がある。だから、ちょっとぐらい決まりを破って、様子でもうかがうぐらいいいじゃないか。もし怒られたら「あ、申し訳ない、便所に行こうと思って、酔って間違えた。いや、これは失敬」とはぐらかしてしまえ。「魔が差す」もとい「下半身の制御不能状態」に陥って、私は、音を立てないように、そっと戸を開けた。
そこには、鶴がいた。
私は「なんで鶴がいるの?」と思った。
だってここは私の家だから。
外じゃないから。
外でもそんなしょっちゅう見ないけどね。
鶴か。
鶴?
は?
鶴じゃん。
鶴ねえ。
鶴といえば。
私は、女性が来る前の日、薪を背負って雪道を降っている際に、猟師の罠にかかった一羽の鶴を助けたのを思い出した。「情けは人のためならず」とは「人にかけた情けは、巡り巡って自分のところに返ってくる」という意味であって、誰かに冷たくするんじゃなくて、情けをかけておくに越したことはないよね、もしかしたら得するかもしれないし。との打算を含んだことわざであるから、私はそこに「ハート」を感じず、好きな言葉ではない。しかしながら、「無償の愛」が美徳だと信じ抜いた結果、今のような貧乏、困窮を招いている。
そうは言えども、人に優しさ、情けでさえも打算のうちに含めるのは果たして本当の善行なのだろうか?やらない偽善よりやる偽善か?偽りであることに変わりはないのだから、行動で示されるほうが良い、すなわち、得だ。私は得をしたい。だが、目の前で苦しんでいるのは「鶴」だ。猟師の食い扶持を奪うことと、目の前の鶴を助けること、どちらに私にとって利があるのだろう。
答えは後者だ。なぜなら、目の前の「命」を助ける行為は、私のハートを晴れやかにする作用があって、その日1日においては明るく振る舞うことができて仕事に対しての能率とモチベーションの向上につながるのに対し、鶴を見殺しにしてしまえば、私のハートが曇り、もやがかかるのみならず、猟師の腹を満たすだけだから、損得勘定の秤にかけて、「私自身のハート」「鶴の生命」「仕事の成果、もっと言えば、ババアを守ること」に結びつく、これらすべてを満たすため、私は「鶴の罠を外す」行為を選択した。鶴は舞い上がって、天空に消えた。美しいと思った。ごちゃごちゃと理屈立ててみたけれど「美しいと感じることのできた自分の感情」に気がつけたのが、私にとっては、もっとも嬉しい出来事であった。
—
「鶴の舞い上がる姿を美しいと感じる私」と「ババアを守りたい私」と「戸の向こうにいる女性の姿態を妄想する私」は、いちジジイの形をした器の中に納められている。この三角形は、歪になったり均一になったり、広がったり狭まったり、色がついたり白黒になったり、ぐるぐると回転したり静止したりしながら、雪の積もる藁葺きの屋根の下、見えないが確かにそこにあるのだ。
しかし、現実として存在しているのは、ただの「突っ立っている、すけべジジイ」なのだった。女性、もとい、鶴は「覗くなってあれほど言いましたよね?いや、本当にありえない。一生反省してください。虫、豚、茄子、なまくら、ブルシット、それでは、さようなら」と早口でまくし立てたのだが、私の耳には「ケンケン」としか聞こえなかった。びっくりしていたし、ジジイの耳だし、あと、鶴の喉から聞こえる音って、人間の言葉を喋っていたとしても「ケンケン」に聞こえるんですよ。あんまり聞く機会、ないかもしれないですけど。
鶴は、矢のように鋭くなって、私の左の頬を掠めて飛んで行った。頬が冷たく切れて、血が流れた。ババアは「ケンケン」に反応して目覚め、事態を把握し、泣いた。泣いて泣いて泣いた。そこから私の反省が始まって、雪が融けて、緑が芽吹いて、コメが実って、雪が降った。


 JET
JET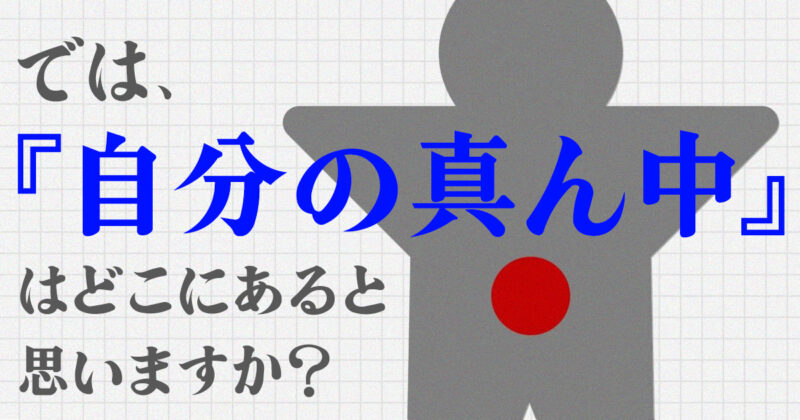
 ペンギン
ペンギン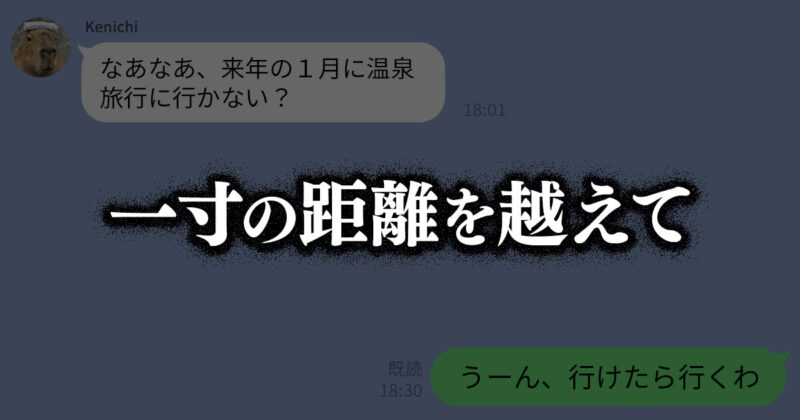

 梨
梨
 彩雲
彩雲
 鳥角
鳥角







