中学三年生になってすぐの頃から、引退の年の部活動に勤しむわけでも、皆より少し早めの受験勉強に精を出すわけでも、友人か親友か曖昧な同級生達と気ままに時を過ごすわけでもなく、一日の授業を終えてすぐに校内の図書室に向かうのは僕の日課になっていた。

通っていた中学校の図書室は、何曜日に来ても何時までいても、いつも利用者が少なかった。
特段致命的な欠点があったわけではなく、ただ学校から歩いて二十分もしないところに、大変立派な市民センターと、それに併設された、大変立派な図書館がどんとそびえていた。
並べられた本の豊富さは勿論のこと、小綺麗な自習スペースやちょっとしたカフェまで備わっていたこの立派な図書館は、数駅先や隣町からも利用者が多く、結構な範囲にその立派さが知られているようだった。
そして立派さの恩恵を受けたいのは中学生も例外ではなく、自分の中学校の図書室と立派な図書館、天秤にかけるまでもなく皆一様に『立派』を選択していた。
中学校の図書室、これが営利を目的とした場所であれば何らかの対策を施したのだろうが、たかが学校内のいち施設、来ないならそれはそれで結構。
そう言うかのように、一応居る司書の職員も、観念したように毎日何時になっても眠りこけている始末だった。
『新しく置いてほしい本を募集します』と書かれた投票用紙が司書の隣で、司書が船を漕ぐのとリンクするように、空調に揺られて不規則になびいているのが、いつ見ても哀愁を誘った。
*
一度この司書が眠っている隙に、読書なんて毛ほども興味が無さそうな男子生徒達が忍び込み、クスクスと笑いながら用紙に何か書き、箱に入れたのを横目で見たことがあった。
彼らが立ち去ったあと箱の中を覗き見ると、『グラップラー刃牙 全かん!』と書かれた紙があった。
二週間ほど経った頃に室内をうろつくと、奥の棚の隅の方に、『範馬刃牙 3巻』が申し訳なさそうに置かれているのを見つけた。
少しだけウケたが、何故範馬刃牙の3巻だけ置いてあるのかは全然分からなかった。
2巻以前も4巻以降も置いてある様子が無かったし、『グラップラー刃牙』『バキ』を差し置いて『範馬刃牙』をチョイスしたのも謎だった。
司書の家にたまたまあったのだろうか。範馬刃牙 3巻だけが?そんな奴いるか?
あの男子達は結局、僕が知るなかでは範馬刃牙 3巻を借りに来ることはなかった。
*
話を戻して、そんな試合放棄した図書室をよく利用する生徒は僕と、もう一人の女子生徒ぐらいだった。

彼女はいつも入口から一番離れた席で、窓に相対するように座って本に視線を落としていた。
図書室の窓側は西側に面しており、だいたい夕方の四時過ぎになると、いつもエグいぐらいの量の西日が彼女の顔面に降り注いでいた。

失明しないのか?という僕の心配を他所に、彼女は表情ひとつ変えず読書を続けていた。
彼女に当たる西日は日増しに強く長くなり、それを毎日眺める僕に、少しずつ夏が近付いているのを感じさせた。

隣の隣のクラスで、保坂さんというらしい。下の名前は知らなかった。
名前なんて誰かに聞けばすぐ分かっただろうが、当時の僕は、毎日図書室でだけ見る彼女が具体的になってしまうのが怖くて、そういった行動を起こせずにいた。
隣の隣のクラスが体育をしている時も、いつもグラウンドから目を背けていた。
一度保坂さんが教室の前で誰かと親しげに話しているのを遠目で見かけて、それから、隣の隣の教室の前はなるべく通らないようにした。
自分の中でだけ、保坂さんを『特別』にしていたかった。
*
保坂さんはロングヘアと呼ぶには少し短い黒髪を、赤色と呼ぶには少し薄暗いヘアピンで留めながら、いつも同じ一冊の本を読み耽っていた。
表紙も背表紙も真っ黒で、遠目ではそれがどんな標題かは分からなかったが、保坂さんを知って二日目に本を探すフリをして覗き込むと、表紙に薄い銀の縁取りで『ぎしき』と平仮名で書かれていた。
キモいな、と思った。
お世辞にも趣味が良さそうな本ではなかった。
が、『ぎしき』を熱心そうに読む保坂さんのことは、どうしても好意的な目でしか見られなかった。
毎日一方的に会うごとに、少しずつ、残りのページ数が少なくなっていくのが遠目で見て取れた。
何となくだが、『ぎしき』を読み終えると、保坂さんはもう図書室には来ないような気がした。
そうでなくとも、もうすぐ本当の夏がやってきて、本格的な受験勉強が始まる。
保坂さんだって、最寄りの塾に通って、夏季講習のひとつでも受けに行くかもしれない。
そう考えると、自分が勝手に作った『特別』が、少しずつ遠ざかっていくようで怖かった。
*
僕は何度か息を大きく吸って、吐いて、意を決して、だけど大きな音が鳴らないようにそっと椅子を引くと、立ち上がって彼女の方に歩を進めた。
別に急な告白がしたいわけではなく、いや、したいかどうかも分かっていなかった。
何のプランも無く、ただ、『特別』に近付くたびに、呼吸が少しだけ楽になるような気もした。

「保坂さん」
声をかけてしまった。どうしよう。
声をかけてから気付いたが、本当に僕は保坂さんのことを何も知らなかった。
無視してくれ、と一瞬、謎の願いも頭に浮かんだが、保坂さんは『ぎしき』から僕に視線を移して、不思議そうな顔をしてしまった。
「ええと、その、その本、よく読んでるよね。ぎしきって、あの儀式?保坂さんって結構そういうの、いや、そういうのっていうか。サブカル?みたいなの興味あるんだ?あ、き、気分悪くしたらごめんね!そうじゃなくて、なんて言うか、その、良いなって思って!僕も、あ、僕は2組の相沢って言うんだけど、初めまして、はは、は。ええと。僕もそういう、ミステリアスな本?好きだからさ、よかったらどんな本か教えてほしい、っていうか、急にごめんね?はは…」
脳は一切介さず、口の周りの筋肉だけを使って、一方的に、何のまとまりも無い内容を、僕は保坂さんに向かって矢継ぎ早にぶつけ続けた。
途中で何度も止まってくれと念じたが、止まって沈黙が訪れてしまうことの怖さが、それを許さなかった。
やってしまった、と僕は顔を青ざめた。
よく知りもしない男から急に捲し立てられて、僕が逆の立場なら、単純に怖いだろう。
言葉をぶつけ終えたあと、保坂さんの顔をロクに見れずにいた。

「…それって、」
保坂さんは立ち上がって、パチンパチン!と二回指パッチンをした。
初夏の湿気なんて吹き飛ばすような、快音二連発。
僕は驚いて視線を保坂さんに向けた。
「それって、シャーマンキングってこと?」
「え?」

シャーマンキングってことって何?と言う隙すら与えず保坂さんは白目を剥き、眉間にビクビクと太い青筋を立てながら、欽ちゃん走りで図書室の中を動き始めた。
呆気に取られる僕を尻目に、保坂さんは「ラブチャ〜〜〜〜ム!!」と叫び、備え付けの椅子や机をギリギリで巧みに避けながら走り続けた。
よく見るとすれ違うたびに、椅子や机を手の平で『撫でて』いた。
めくれて見えた保坂さんのおへそには、これでもかとピアスが開いていた。
唇の両端からはブクブクと泡が出てきており、その泡はどれも数ミリ程度の均等な大きさだった。
ようやく気になって、僕は一瞬、先ほどまで寝ていた司書の方を振り向いた。
司書は一心不乱にメモを取っていた。
僕は落ち着くために、ポケットからチーターハムを取り出して食べた。
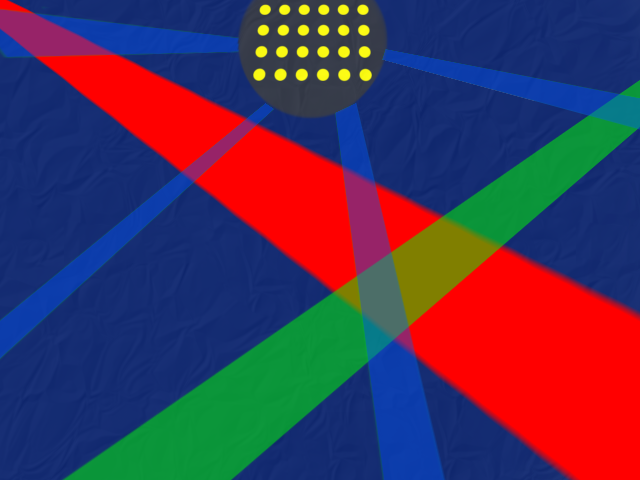
夕日が照るなか、天井に吊るされたミラーボールから三色の光が何本も降り注いだ。

保坂さんは走りながら「ふんふん♫ふんふん♫八代亜紀〜♫」とラッキーマンのOPをうろ覚えで口ずさんでいた。
その間に幾つか、普通に椅子にぶつかり、椅子を倒した。
司書は口に手を押さえて泣いていた。
僕はストレスで、スキンヘッドの頭を掻き毟った。 頭には血がべったりついていた。
頭皮ではなく、両手の爪がズタズタになっていた。
保坂の『技』が炸裂したのだと直感的に分かった。
「…」
図書室全体を十九周か二十周程して、保坂は僕の目の前に戻ってきた。
両手をダランとさせて、は?と言いながら此方を睨んできた。
あ?と言いながら睨み返すと、保坂の口が大きく開き、ヌロッ…と真っ赤なマウスピースを吐き出した。
保坂が手で受け取ろうともしなかったそのマウスピースは、当たり前のように自由落下し、ベチャッと床に叩きつけられた。

「嗅いでみて」
そう言い残すと、保坂は再び欽ちゃん走りで図書室を後にした。
ジリジリジリジリ!!とけたたましい音でサイレンが響き渡った。
机に目をやると、『ぎしき』が紫の炎に包まれて燃えていた。
「…」
火災報知器が警鐘を鳴らすなか、僕はしゃがみ込み、床に放置された唾液まみれのマウスピースに、スン、と鼻を寄せた。
二度、三度と鼻を鳴らし、僕は首を傾げ、マウスピースを指でつまんで裏返し、また鼻を鳴らした。
「お日さまの匂いがする…」
外はすっかり日が沈み、熱心な野球部の掛け声と報知器の後、図書室に駆け寄る職員たちの足音、咽び泣く司書の嗚咽が僕の耳に入っていた。
 店長
店長







