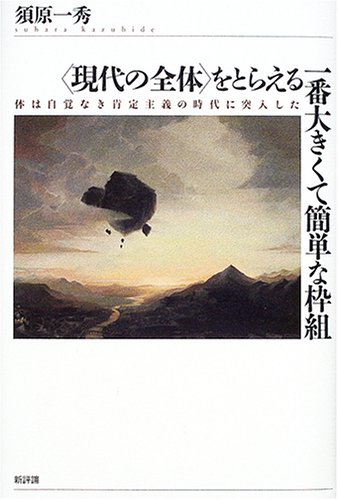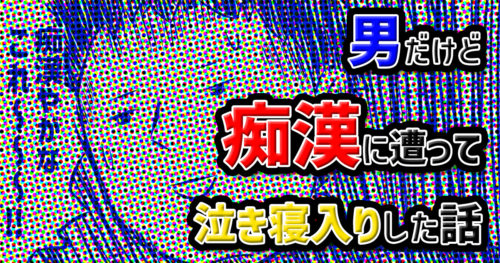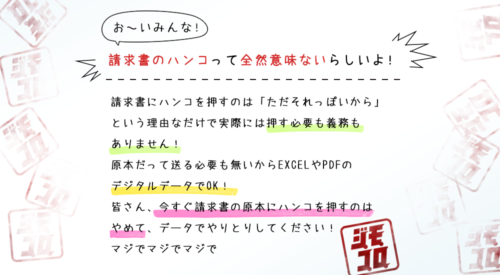須原一秀「現代の全体をとらえる一番大きくて簡単な枠組」
これは「西洋哲学史」を扱った本である。
しかし、「哲学の入門書」ではない。
なぜ入門書ではないのか?
この本は、哲学はすでに「溺死」したと主張しているからだ。
歴史上、「哲学」と呼ばれた運動はすでに終わっており、それは一部の人間にとっては常識なんだが、大半の人はまだ「哲学」が存在していると思いこんでいる。だからその誤解をときたい、というふうにこの本は始まるのだ。
変な本である。
私はこの本を、「哲学って要するに何なんだよ?」「自分と関係あんのか?」と疑問に感じたことのある人にすすめたい。
ということで、内容の紹介である。
「思想」を5×2に分類する
「哲学はすでに溺死している」という話に入る前に、「そもそも哲学とは何なのか?」という話である。
著者の須原一秀は、「思想」と「哲学」を分けることを提案する。
「思想」とは何か?
それは、人々の色々な「ものの考え方」のことである。「思想」は日々の雑談にも、ネットの書き込みにもあふれている。誰だって思想を持っている。それは単なる「ものの考え方」だから、とくに珍しいものではない。
須原は、代表的な「思想」を5×2に分類している。
個人主義ー全体主義
結果主義ー心情主義
科学主義ー神秘主義
真実主義ーソフトウェア主義
肯定主義ー否定主義
これは現代に生きている人ならば誰でも「実感」できる思想だという。
「主義」という言葉が大げさに響くなら、「個人主義ー全体主義」を「個人を優先する考えー全体を優先する考え」としてみればいい。「全体」というのも、「国家」ではなく、「家族」や「会社」とすればいい。するとピンとくるはずだ。これは、「自分を優先するか、みんなを優先するか」という昔からある対立に名前をつけたものなのである。
「結果主義ー心情主義」も分かりやすい。「結果が出ないと意味がないよ」と考えるか、「それでも頑張ったことを評価してあげたいよ」と考えるかの対立である。
「科学主義ー神秘主義」の場合は、「科学がすべてを説明してくれるはずだ」と、「科学で説明しきれない神秘的なものがあるはずだ」の対立だろう。
「真実主義ーソフトウェア主義」の「ソフトウェア主義」は、「人それぞれだよね、色々と条件も違うんだし」という考え方のことである。SMAPの『セロリ』に歌われた「育ってきた環境が違うから、好き嫌いはいなめない」というやつだ。相手と意見が一致しない時、こう考える人は多いのではないか。
「肯定主義ー否定主義」は少し分かりにくい。
須原は、「人間の不合理なところ」を丸ごと肯定することを肯定主義、否定するならば否定主義としている。例えば、人間には暴力的な面もあれば、嫉妬深い面もある。怠惰な面があれば、勤勉な面もある。馬鹿かと思えば、賢明だったりする。そのようなゴチャゴチャしたものを「そのまま肯定する」ことを、須原は「肯定主義」と呼んでいる。
逆に、そういった人間の多様な側面のうち、ある部分を強く否定しようとするならば、「否定主義」ということになる。よって、「暴力は絶対にいけない」とか「不倫は何があっても許されない」という発想は、ここでは否定主義と呼ばれることになる。
以上の「5×2の思想」は、誰でも無自覚に採用しているものである。
同時に、人はその場に応じて、矛盾する「思想」を平気で使っている。例えば、「結果がすべて」と豪語するオッサンが、小さな娘の描いてくれた稚拙な似顔絵を見て「その気持ちが嬉しい」と涙するように。
「哲学」と「思想」はどう違うのか?
さて、ようやく「哲学」である。
「思想」と「哲学」はどう違うのか?
「哲学」は、上記の「思想」を厳密に学問化したものなのだ。「厳密に学問化」すると何が変わるのか? 「思想」の時のように、平気で矛盾していることはできない。考えの根拠をたずねられて、「なんとなく」と言うことも許されない。それぞれの言葉には、明確な「定義」も必要になるだろう。
途端にハードルが上がるわけである。
「哲学」においては、「結論を急がなくてもいいじゃないか」「考えるプロセス自体が哲学なんだよ」という主張も却下されるべきだと須原は主張している。
それは「人生論」とか「科学論」とか「学問論」などと呼ぶべき評論活動の話であり、学問としての「西洋哲学」の話ではないことになります。事が「西洋哲学」に及ぶかぎり、そんな控え目でかわいらしい知的活動ではないことは、多少本気で「西洋哲学」に接したことのある人なら知っているはずです。
「哲学」という運動の根幹には、この徹底性があった。それは、対立する様々な「思想」に最終解答を与えることで完全に終わらせてしまおうとする「傲慢なプロジェクト」だったのだ。
しかし冒頭で言ったように、そのような「傲慢なプロジェクト」としての哲学はすでに死んだのだと須原は言う。
哲学の一度目の溺死、そして復活
歴史上、哲学は二度死んだ。
一度目はどこで死んだのか?
古代ギリシャで生まれ、古代ギリシャで死んだ。
何が哲学を殺したのか?
「キリスト教」である。
打ち寄せるキリスト教の大波にのまれて、老衰気味の古代ギリシア哲学は溺死します。これがギリシア哲学ほぼ1000年の顛末であり、最初の「哲学溺死事件」です。
その後、中世の暗黒時代を経て、ルネサンス期に「哲学」は生き返った。
復活した「哲学」は、「経験を重視する立場」と「理性を重視する立場」の二つの流れとして進み、カントによって「統合」された。しかし須原の分類では、カントは「ソフトウェア主義」と「ストア主義(≒神秘主義)」の合成理論にすぎないという。
その合成の手さばきはなかなか巧妙なものですが、内容上、コンピュータ学者にも、認知科学者にも、あるいはストア主義的現代人にも、当面すぐに参考になるものはない、と言わざるをえません。(中略)一般の人があの膨大で難解な内容を制覇して、その苦労に見合うものが見つかる当ては非常に低いと私は考えます。
ニーチェについて
そして十九世紀に突入する。
ここではニーチェについて、「今でも人気がある思想だから」ということで、例外的にページを割いて批判検討されている。
一言で言えば、ニーチェはギリシア的・貴族的・肯定主義者なのですが、十九世紀のドイツという時代背景と彼自身の個人的事情のせいで気持ちが屈折し、必要以上に肯定主義とソフトウェア主義を強調しすぎます。
その結果、ニーチェは普通の人間の普通の生き方を「必要以上に否定する」傾向があるんだが、
肯定主義を称揚するあまり、天下無敵のスーパーマンのように、あるいは無邪気に遊び戯れる子供のように、純粋に永続的に肯定主義を生き切れるかのような幻想を抱くあたりで、ニーチェは嘘っぽくなるのです。
須原は、いまだにニーチェが人気なのは、その文章が「誤解や曲解を煽るように」書かれており、読み手に「窮屈な市民的日常から脱却させてくれそうな幻想を抱かせる」ところにあると指摘する。
しかし、実際のニーチェの生活はニーチェの思想とは程遠いものだった。中年期において、ニーチェは十六歳年下の女に恋をしたのだが、「一度はキスくらいしたかもしれない」関係になっただけで、最後は完全にフラれてしまうのである。
しかし、著作では露骨な女性蔑視と、思いっきり背徳的な言葉を吐き散らかしているのがニーチェです。しかも、本能が道徳に勝つべきこと、そのためには「同情」などまったく無用とまで言うのがニーチェの根本思想です。
徹底的に考え抜いた結果、そこまでの哲学に到達していた四十歳に近い男が、生涯最大の恋愛の最中に、二人きりのチャンスはいくらでもあったはずなのに、強姦とまでは行かないまでも、多少強引な、あるいは詐欺的な行為に及ぶこともなかったらしいとすれば、私たちはどのように考えればよいのでしょうか。
さらに、
この背徳の哲学者は、それ以外にもとくに傍若無人な振舞いに及ぶこともなく、結局、「善良な一市民」として、母と妹以外にあまり周囲に迷惑をかけることもなく、怒りっぽい――ということは、かなり欲求不満の――独身生涯を閉じたらしいと知る時、「なんだ、口ばっかりか」と思ってしまうのは私だけではないはずです。
〇哲学の二度目の溺死
そして二十世紀を迎える。
二十世紀は新しい哲学を生まなかった。二十世紀前半では、フッサール、ハイデガー、論理実証主義者たちが、これまでの哲学の半端さを改善するために立ち上がり、「基礎からの哲学の再構築作業」に取りかかったのだが、「三者ともに見事に失敗」してしまったという。
この失敗によって確認されたことは、十九世紀までのすべての哲学が学問的に弱くて半端であること、それにもかかわらず、それを「改善する道筋」も、「抹消してしまう手続き」も誰にも確立できないということでした。
その後、哲学者たちは試行錯誤を繰り返すが、とくに結果の出ないままに時は過ぎてゆき、それぞれがそれぞれの専門領域に、つまり「狭苦しいタコツボの中に」入りこんでしまった。須原は、自分の所属する「分析哲学」が特にそうだったと率直に認めている。
このような挫折で気力・体力が弱っている時に、第二次世界大戦後に大きくうねり出した「大衆肯定主義」の大波が襲ってきます。その大波に対する否定主義的・教養主義的抵抗運動とともに、数度の浮き沈みを経由した後、結局、哲学は溺死してしまいます。
これが二度目の「哲学溺死事件」です。
ルネサンス期に息を吹き返したはずの「哲学」は、つまり「真理を求める運動」は死に、現在も生き返っていない。人々は今でも昔と変わらない様々な「思想」を持っているが、それに「最終解答を与えようとする挑戦」は終わったのだ。
「現代哲学」というものは、どこにも存在しないと言うべきです。存在するのは、「古代からの何の変哲もない十種類の思想」と「それらの相互批判と自己弁護」だけだったのです。
「哲学の二度の溺死」を駆け足で記述し、「哲学の不成立」を確認した須原は、「現代が出口のない時代に見えるのは、単に出口から出てしまったからだ」と主張する。そして、「様々な考えが乱立する猥雑で不潔な民主主義」を肯定する。こうして、書名である「現代の全体をとらえる一番大きくて簡単な枠組」が提示されるのだが、さすがにこの紹介は長すぎる。あとは実際に本で読んでみてください。
〇須原一秀の自死について
最後に、著者の須原一秀について少しだけ。
この本は2005年に出版されたが、翌2006年、須原は「一つの哲学的プロジェクト」として自死を敢行した。その経緯は、死後に出版された「自死という生き方」に書かれている。興味のある人は読んでみてください。自分の死を扱っているのに妙な明るさがあって、こちらも面白いですよ。

“現代の全体”をとらえる一番大きくて簡単な枠組―体は自覚なき肯定主義の時代に突入した
- 作者: 須原一秀
- 出版社/メーカー: 新評論
- 発売日: 2005/02
- メディア: 単行本
- 購入: 8人 クリック: 175回
- この商品を含むブログ (12件) を見る